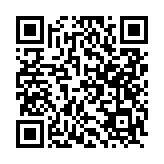|
最新更新日:2022/01/12 |
|
本日: 昨日:0 総数:1290 |
03まず地図で小牧をさがしてください
まず、中部地方の地図を開き、日本第三の都市「名古屋」の北西にある小牧を見つけてください。僕たちの故郷「篠岡」は、この小牧市内にあるのです。その面積約二八・三一平方キロメートル、人口は約八千三百六十人。全体が丘陵地帯で、七つの地区と開拓地区とにわかれています。僕たちの学校は篠岡のほぼ中心にあるが、急な坂が多いので通学はたいへんです。市の中心地「小牧」にいちばん近い地区「下末」のように増々発達する地区もあれば、学校から歩いて二時間以上も時間を要する地区もあります。
それでは、地区別にそのようすを説明しましょう。篠岡の北東の大山地区は篠岡のいちばん奥にあり、人口は、四百十数人で、山がちな所です。すぐ隣りに観光客でにぎわう犬山市がありますが、余り結びつきはありません。庄内川に注ぐ大山川の源がこの大山地区にあります。険しい山が多く、ずっと奥に石金地区という、家が三軒しかない寂しい所があります。大山地区まで行くのに狭い一本道を約一・五時間位かかります。しかし、最近はゴルフ場ができるとか、大山スカイラインができるとか、温泉が出るといっているので期待は大きいでしょう。大山地区の西にある野口地区は人口千八十余人で、水田が大山地区に比べ多くなります。道路も舗装されていて景色のよい所です。いま人気を呼んでいる明治村へ行くのに、いちばん近い地区です。大山地区と野口地区とを合わせて大野地区といいます。 大野地区の西側にあるのが林地区です。人口は七四〇人程度。篠岡中学校の所在地であり、幼稚園もあります。田畑がいっそう多くなり、二重の塔の建っている信貴山をよく見ることができます。そのまた西側にあるのが池の内地区です。人口千二百七十数人で、篠岡の中心地です。篠岡支所、篠岡農業協同組合、篠岡小学校、篠岡郵便局などがあります。池ノ内と林と合わせて、池林地区と呼びます。 池林地区の南南西、約二・五キロメートル位離れたところに上末地区があります。人口は千二百二十人ちょっと。ここは今、東名高速道路が建設されて、小牧インターと春日井インターの中央部でいちばん景色のよいところとされています。ここも現在発達しつつあります。小牧・長久手の戦いで有名な小牧山が一目で見渡せます。上末地区の南側に下末地区があります。人口は千二百五十数人で篠岡内でいちばんよく発達しています。交通の便利がよく、名古屋方面へのバスもかなり出て、最近では交通量が多くなったため、中心の十字路に信号機がとりつけられました。また、軽工場もかなりあり、警察の学校も建てられています。こうして今や下末は篠岡の玄関口として、どんどん発達しつつあります。下末、上末西部を合わせて末地区といいます。 末地区から東へ、隣りの春日井市内の桃山町を越した所に大草地区があります。人口は二千人近くで、面積は篠岡一です。地区は東西にわかれて全体が盆地状になっており、山がちです。交通の便は比較的よく、バスの終点でもあります。最近は木工所などが進出したり、東名高速道路と中央道路の分岐点、小牧ジャンクション、それに「桃花台ニュータウン」といって、大きな計画都市が建設されようとしています。その他、大草周辺に高根とか、小牧ヶ丘といった開拓地区もありますが、交通の便が悪く、まだ発達していません。しかし、果樹園が多くあり、篠岡名産のももなどが植えてあります。 今まで述べてきたように、僕たちの故郷「篠岡」は、年ごとに発達しつつあり、僕たちがおとなになるころは、きっと立派な近代都市に生まれ変わるでしょう。  02郷土を紹介する意義
郷土を紹介する意義 学校長 柴田 護
毎年卒業生の諸君が文集を作って中学校生活の想い出を残しておりますが、今年は郷土に関連した神社仏閣、人物、伝説、年中行事等を、みんなで手わけして調査研究し、それをできるだけ事実に忠実なものであり、将来の参考になるものであるように念願しております。私たちは自分の身近にあるものでも、案外うっかりして知らずに見すごしてしまうことがずいぶんあります。篠岡に生まれ、この地で育った皆さんが遊びたわむれた神社の境内や、お寺庭、何気なしに参加してきたいろいろの行事、おじいさんや、おばあさんから聞いた昔のお話等、一つの観点を定めて眺めてみると、そこに今まで知らずにすごしてきたことが、はっきりして種々意義を見出したことと思います。「温故知新」ふるきをたずね新しきを知るという意味からも、皆さん自身が実際に、その場へゆき、年とった人の話をきいたり、資料を見せて貰ったりして、まとめあげた記録が諸君自身の成長に役立つものであることを期待いたします。しかし、皆さんの調査が完ぺきなものであるとはいえません。将来あの時の自分の調べたことはまちがっていたと気づくことがあるかも知れません。そうしたことが判ればそれだけ皆さん自身が勉強し、成長したことになると思います。お互いに協力して作りあげたこの記録は、ささやかなものであるかもしれませんが、中学生活の最後に自分がとりくんで研究し、調査したたいせつな宝物です。いつまでも可愛がってやってください。 01篠岡百話序
『篠岡百話』編集の主旨は、国語科「三、効果的な説明」目相手を考えて説明しよう……『実際に書いてみよう』の問題中「自分たちの郷土を、いろいろな角度から紹介する」をとりあげて各自が書いた説明文をまとめることにある。
だから、この『篠岡百話』は、郷土史話の体裁をとりながらも、究極は説明文で書かれた生徒の作文を集録したものに過ぎないことを最初に断っておかねばならない。 それでも、この『篠岡百話』編集を思いたったのは、昭和四十二年の七月ごろで、そのとき書かれた作文も幾つか本誌をうめてくれたから足かけ三年の大勢の耳と目の結晶であると確信する努力の作品集であることも間違いない。 時、あたかも明治百年にあたり、ことしの卒業生が、明治百年度の卒業生ともいえる。こういう意義ある年に、意義ある卒業文集を編むことは、だけでも意義が高まる。ほんとうに心からご苦労だったと諸君に申しのべたい。 ただ、残念なことは、この書物が大勢の人に渡らないという点だ。あくまでも授業の結晶であり、卒業文集であって、世に問う出版物でない点だ。みんなが調べて書いたこの郷土紹介文は、公にしてもあまりある貴重な値うちがあることをだれも疑ってはいない。 0-2復刻合本版の「発刊にあたり」 篠岡中学校は、昭和四十三年以来三年生が卒業に際し、卒業文集にかわって、自分たちの郷土をいろいろな角度から研究し、それを一冊の研究物にまとめ発行してまいりました。これが「篠岡百話」であり、既に十集におよびました。 小牧市篠岡地区は、ご存知のとおり今や桃花台ニュータウン建設が急ピッチに進められており、郷土篠岡が激変しようとしています。即ち自然・地形・交通・産業はもとより、昔から培ちかわれてきた人情・風俗・習慣等が消え去ろうとしています。 こうした中にあって、「篠岡百話」は資料保存のうえからも、又、郷土民俗研究物としても、高く評価されるに至りました。しかしながら、十年間にわたる継続研究発行であったため、一集から十集まで、全集保持する人が少なく、最近に至って各方面より、「篠岡百話」復刻合本版の編集発行を要望され、期待されています。 篠岡中学校は本年四月創立三十五周年を迎え、この時にあたり、桃花台地内に本校より、桃陵中学校を分離開校させることになりました。こうした諸状勢をふまえ、この機会に「篠岡百話」復刻合本版を発行し、各位のご期待に応え、こうした地味な研究活動… 郷土愛教育を永遠に残そうと決意いたしました。幸い編集委員各位の絶大なるご協力を得、更に各種団体のど後援ご推薦を賜わり、ここに発行の運びになりました。各位に謹しんで感謝いたします。 又、この事業が十年間にわたり、直接この研究に参加した一三五九名の同窓生はもとより、五、○○○名になんなんとする、篠中同窓会の堅い団結のきずなとなり、母校愛・郷土愛の源泉となり、更に学区の旧来の方々は勿論のこと、新しく桃花台に入居された方々の温いご支援ご協力を得ることにより、篠岡地区新旧住民共々が、故きを温ね新しきを知ることができ、新しい郷土づくり、街づくりに役立てば幸いと思います。 0-3篠岡百話復刻合本版の編集にあたって
篠岡百話復刻合本版の出版にあたり、次のような方針で編集しました。
一、篠岡百話は、十年以上の長期にわたる出版物であるため、初期のものは、印刷が悪く、丁裁も不揃いになっています。 完全復刻という方法も検討しましたが、第一集から第十集まで(全巻)新たに版を組み直しました。 一、篠岡百話は、生徒が直接古老の方などを尋ねて聞きとり調査をしたり、文献を調べたりしてまとめあげたものです。こうした調査の在り方の意義を重んじ、できるだけ、原本を尊重する方針で校正・修正をしました。従って、句読点の誤り、誤字、文章や内容が明らかに誤っているもののみにとどめました。 一、地図などで折り込みの頁のものは、製本の関係からA5版大に縮少してあります。 昭和五十七年七月 篠岡百話復刻合本版編集委員会 0-1復刻合本版の「はしがき」
篠岡百話復刻合本版編集委員会 委員長 西村 大進
篠岡中学校創立三十五周年の記念すべき年を期して「篠岡百話」の復刻合本版の発行を企画され、このたび刊行を見るに至ったことは有意義であり、地域住民として喜ばしいことであります。 振り返ってみますと「篠岡百話」は、篠岡中学校の卒業生が昭和四十三年度から十年間の長きにわたり(第一集〜第十集) 三年生全員(千三百有余人)が研究に参加しております。この研究は生徒が先生のご指導により、篠岡地区内をくまなく踏査・探訪したり、古老・有識者等から聞きとり調査を実施し、その結果をまとめたものであります。 先輩たちによって築きあげられた、伝統と業績は後輩生徒の研究への励みともなり、大きな力となってまいりました。苦心して調査したり、まとめたりする過程で得た体験は貴重なものであり、郷土を再認識するよい機会ともなりました。 このような地域社会に密着した郷土研究が広く皆様方から認められ、地域の方々は勿論、広く市民・同好の各位から愛読されることを期待しております。 最後に「篠岡百話」復刻合本版の編集ならびに刊行につくされた関係各位のご努力と、ご後援で推せんいただいた各種団体のご協力に対しまして、衷心より敬意と感謝を表する次第でございます。 昭和五十七年七月 |
篠岡小中連携
〒XXX-XXXX 住所:XXXXXXXXXXXXXXXX TEL:XX-XXXX-XXXX FAX:XX-XXXX-XXXX |