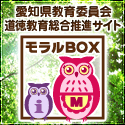|
最新更新日:2024/06/01 |
|
本日: 昨日:81 総数:617722 |
1月10日(金) 110番の日



気温もこの時期としては高く、今日は穏やかな1日となりそうだ。気温は3月下旬ころの14度くらいまで上がるということだ。今年の冬はいったいどこに行ってしまったのだろうか?そんな穏やかな天気なので、子どもたちのテンションも自然と上がり、あいさつの声も大きくなる。この気持ちのよい朝はいつまで続くのだろう? 今日は警視庁が1985年(昭和60年)に制定し、翌1986年(昭和61年)から実施している「110番」の日だ。制定された理由は日付を見ればわかるはずだ。小学校になれば、110番と119番はどこにつながる電話番号かはちゃんと知っているはずだ。命や安全を守るために絶対に知っておかなければならない電話番号だが、できれば1度も使うことのない、平和で幸せな人生にしたいものだ。 今日も大きなけがで救急車を呼ぶことのない、短期と同じような穏やかな日になりますように・・・。 1月9日(木) とんちの日・クイズの日

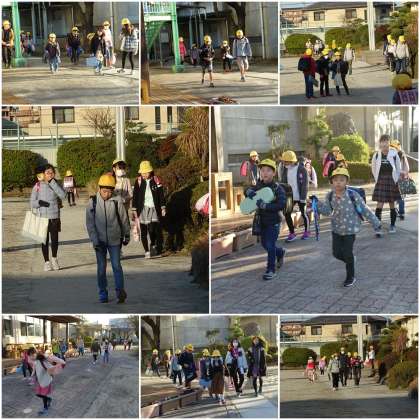

今日は「とんち」で有名な「一休さん」にちなんで「いっ(1)きゅう(9)」(一休)と読む語呂合わせから、「とんちの日」、そして「とんち」を「クイズ」という意味にとらえて「クイズの日」となっている。一休さんと言えば「屏風の虎退治」や「このはし渡るべからず」などが有名な話だが、「とんち」(頓智/頓知)とは、その場に応じて即座に出る鋭い知恵という意味で使われている。ひょっとすると、AIが発達していくこれからの時代に、人間として最も重要な力かもしれない。「とんち」には、知的ユーモアがあり、人々の心を和ませる力もある。毎日の学習で得る「知識」を、状況に応じて即座に活用できる「知恵」に変えていきたい。 1月8日(水) 正月事納め



今日は、お正月に飾られていた、門松や注連縄(しめなわ)の飾りを取り外す「正月事納め」の日だ。地方によっては15日まで飾る所もあるようだが、最近は7日までとするところが多いそうだ。 子どもたちも「正月気分」とは「さよなら」をし、今日明日くらいまでにスパッと「学習モード」に切り替えてほしい。6年生の3学期の登校日はあと48日、1年〜5年は50日だ。ボーッとして過ごしているとあっという間に終わってしまうので、気合いを入れて毎日の学びに向かっていってほしい。 学級活動 課題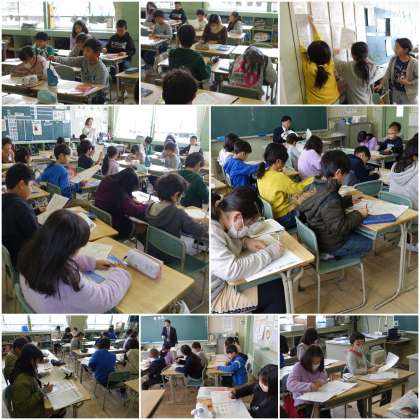





日誌以外にもプリントが何枚か宿題として出されていたようだ。 お年玉でもらったお金は貯めておくのもいいけれど、 宿題はためても、ろくなことがない・・・。 「やってあるけど、持ってくるの忘れました!」といって、 今日帰ってから必死に宿題をやる人は・・・いませんよね? 学級活動 課題



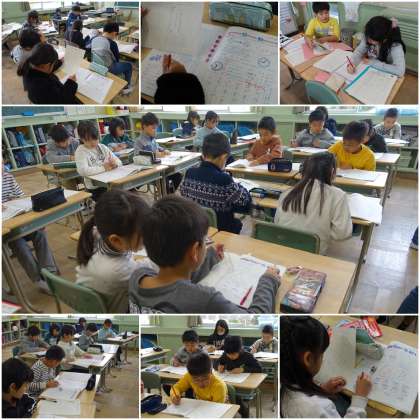

夏休みほどではないけれど、冬休みも結構宿題があった・・・。 始業式の風景「課題提出」と「日誌の答え合わせ」・・・。 今日、全部提出できたかな? ひょっとして・・・もしかして・・・まだやっていない人いる? 1月7日(火) はじまり



さあ、子どもたちの令和2年(2020年)が本格的に始動した。子どもの頃からの小さな努力は、やがて大きな夢につながって行く。「わからないこと」や「できないこと」を、粘りと根性で克服していくことを思いっきり楽しんでほしい。 勇者の帰還

心とからだを癒やす「家庭」へと帰還します。 子どもたちにとって素晴らしい冬休みになることを願っています。 2学期も三ツ渕小学校への、 温かいご支援・ご協力ありがとうございました。 よいお年をお迎えください・・・。 通知表



「算数の計算練習よくがんばったね」 「ノートの字がすごくきれいになったね」 「そうじよく頑張ってくれたね」 「友だちにやさし声かけができたね」 「友だちの意見を一生懸命聴くことができたね」 子どもたちはできないことがあって当たり前、 わからないことがあって当たり前。 だから勉強するのだから・・・。 子どもだけじゃなくて、大人だってほめられるとうれしい。 ほめられると、またがんばろうと思う。 持ち帰った通知表は、お子さんの成長をほめるためのものです。 いいところを見つけて、たくさんほめてあげてください。 お母さん、お父さんは 毎日見ているから気づかないかもしれないけれど、 お子さんの心と身体は大きく成長しています・・・。 間違いなく、できるようになったことが増えていますから・・・。 2学期終業式・表彰伝達





表彰伝達では、以下の児童のみなさんが書道・ポスターコンクールなどで優秀な成績を修めました。 ○小野競書会 特別賞 2年 志村 沙那 秀逸 1年 中嶋 栞里 秀逸 1年 早稲田 みさき 秀逸 2年 舩橋 栞奈 秀逸 3年 早稲田 彩乃 秀逸 4年 飯田 愛香 秀逸 4年 片出 凛 秀逸 6年 林 愛埜 佳作 3年 堀部 雄太 佳作 5年 稲垣 奈佑 佳作 5年 大澤 知生 佳作 6年 早稲田 敦基 ○JA共済書道コンクール 半紙の部 金賞 6年 関戸 亜莉 銅賞 5年 大澤 知生 条幅の部 銀賞 1年 中嶋 栞里 佳作 2年 志村 沙那 ○赤い羽根:書道 佳作 3年 堀部 雄太 佳作 4年 増田 翔英 佳作 5年 大澤 知生 佳作 6年 林 愛埜 ○赤い羽根:ポスター 佳作 1年 浅田 陽翔 佳作 2年 増田 大輝 佳作 3年 工藤 大駕 佳作 4年 鈴木 柚果 佳作 5年 林 拓冶 佳作 6年 関戸 亜莉 ○交通安全ポスター 1年 伊東 快晟 多くの児童のみなさんが、学校害でも活躍してくれていることをうれしく思いました。受賞したみなさん本当におめでとうございます。 表彰伝達の後、1年の小川詩乃さんと4年の増田翔英くんが、児童代表スピーチとして2学期がんばったことや3学期がんばりたいことなどを、みんなにわかりやすく発表してくれました。4年生の増田君は2学期学習した環境問題を考えるプレゼンテーションまでしてくれました。 代表スピーチの後、校長先生の話を聴き、校歌を元気よく歌って2学期の終業式を終えました。 校長先生からは、「全員が大きく成長できた2学期だった」「これからもわからないことやできないことに挑戦することを楽しんでほしい」「何度も失敗して成功がある」「夢は実現させるものだ」「あきらめない粘りと根性が大切」「冬休みの安全」などについての話がありました。 表彰が多くて、ちょっぴり長い終業式になりましたが、全員最後までしっかりと話を聴くことができていました。 12月23日(月) 冬至を越え・・・





長いと思っていた2学期も今日で終わりとなるが、一人一人2学期をもう一度よくふりかえり、明日へと・・・そして新しい年につながる1日にしてほしい。 12月20日(金) 平成元年度もあと11日



授業は今日で一区切りとなり、再開するのは年が明けた1月8日からとなる。1年のふり返りをしっかりとし、新年を新たな気持ちで迎えることができるよう、心がけてほしい。また、年末は慌ただしく、交通事故も起きやすくなる。外出時は落ち着いて行動し、自分の命を守ってほしい。 さあ、令和元年度もあと11日・・・残された時間をどんな時間にするかを決めるのは自分だ・・・。 12月19日(木) 暖冬



今日はこどもたちが学校に到着する頃に太陽が姿を見せてくれた。やはり朝は、光のある眩しい朝がいい。 登校日も今日を終えるといよいよあと2日となった。学校から図工などの作品を持ち帰ると思うので、少しだけでいいので家のどこかに飾ってあげてほしい。そして、色使いや構図、人物の表情などを具体的にほめてあげてほしい。そんな一言が子どもたちの明日への意欲へつながる。 12月18日(水) 雨のち晴れ



今週に入って欠席者も減少し、心配していたインフルエンザも流行することなく、2学期を終えることができそうだ。しかし油断は禁物、今までと同じように予防に心がけていきたい。 今日を終えると登校日はあと3日・・・。今日も学びとの出会いを楽しみながら学校生活を送っていきたい。 12月17日(火) 飛行機の日



今日は1903年(明治36年)に、アメリカ・ノースカロライナ州において、ライト兄弟がライトフライヤー号で、動力飛行機の初飛行に成功したことから「飛行機の日」となっている。一昔前は人間が空を飛ぶなんていうことは「夢」であり、実現不可能とされていた。月に行くなんていうことも不可能だと言われ、そんな話をすれば人々に笑われていたものだ。現代では「テレビ」「電話」「ロボット」「インターネット」「電子レンジ」「自動運転」など、一昔前にはSF小説や漫画の世界のものだとされていたものが、現実のものとなり、当たり前のように使う時代となっている。このことからも「夢」は見るものではなくかなえるものであることがわかる。これから先、どんな今まで夢とされてきたものが現実のものとなるのだろうか?子どもたちには夢を追いかけるチャレンジャーになってほしい。 12月16日(月) 電話創業の日



今日は1890年(明治23年)に、東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始した「電話創業の日」だそうだ。いつもの「雑学ネタ帳HP」によると、加入電話は東京155台・横浜44台、電話交換手は女子7人・夜間専門の男子2人が対応したそうだ。また、当時の電話料金は定額料金で東京が40円・横浜35円。この時代、1円で米が15kg買えたため、今の値段にすれば40円は24万円くらいに相当し、当時の電話はとても高価なサービスだったということになる。電話代で月24万と考えると、一般の人たちはほぼ使うことはないものであったことがわかる。時代とともに人々の生活はどんどん変わっていく、そんな時代の変化に対応できるよう、毎日の学びを大切にしていきたい。 12月13日(金) 正月事始め



今日は、煤払い(すすはらい)などをして、年神様を迎える準備を始める「正月事始め」の日だ。昔はこの日に門松やお雑煮を炊くための竹や薪など、お正月に必要な木を山へ取りに行く習慣があったそうだ。学校でも一足はやい11日に大掃除をすませたところだ。 よいことは新しい年につなげ、悪いことは新しい年に持ち越すことがないよう、1年のまとめと新しい年への準備をしっかりし、新年を迎えたい。 だれにも公平に与えられた時間をどんな時間にするかは、自分次第だ。 12月12日(木) 漢字の日



今日は日本漢字能力検定協会(漢検)が1995年(平成7年)に制定した「漢字の日」だ。「いい(1)じ(2)いち(1)じ(2)」(いい字一字)と読む語呂合わせから。日本人ひとりひとりが毎年、「いい字」を「一字」は覚えて欲しいとの願いが込められている。 毎年、その年の世相を象徴する「今年を表現する漢字」を全国から募集し、一番多かった漢字を、この日に「今年の漢字」として京都の清水寺で発表している。清水寺貫主の揮毫でその字は清水寺に奉納される。この行事は1995年から実施されていて、年末の風物詩となっている。(HP:雑学ネタ帳から引用) さて、今年の漢字は何が選ばれたのだろう?ニュースが楽しみだ。 12月11日(水) 百円玉記念日



今日は1957年(昭和32年)に日本で初めて百円硬貨が発行された日ということで「百円玉記念日」となっている。いつものHP雑学ネタ帳には百円硬貨について、以下のように書かれていた。(※雑学ネタ帳から引用) 最初の百円硬貨は、戦後初めての銀貨だった。素材は主に銀(銀60%・銅30%・亜鉛10%)で、図柄は表面に鳳凰、裏面に旭日と桜花、直径は今と同じ22.6mm。それまでは板垣退助の肖像の百円紙幣が使われていた。その後、1959年(昭和34年)、図柄が鳳凰から稲穂へと変更された。これは図柄のみの変更で銀貨のままだった。1967年(昭和42年)、現行の百円硬貨が発行されるが、素材は銀から白銅(銅75%・ニッケル25%)に変更され、図柄も桜の花三輪へと変更された。素材の変更は銀の値段が高くなったことが理由として挙げられる。また、この百円玉に描かれているのは、日本を代表する桜の山桜(ヤマザクラ)である。 注目すべきは、最初の百円硬貨は「銀貨」だったということだ。ひょっとしたら上の写真のような百円硬貨が、家のどこかに眠っているかも・・・。家族みんなでお宝探検隊だ! 12月10日(火) ノーベル賞授賞式



今日はノーベル賞の授賞式があり、リチウム電池の開発に貢献した旭化成の吉野彰名誉フェローがノーベル化学賞を受賞する。リチウム電池は今の世の中にはなくてはならないものであり、これからの時代でもますます重要度が高まってくるものだ。 研究者である吉野氏が語っていたこんな言葉が心に残っている。 ○「好奇心を持って調べていくと、得意なことができ、将来の夢につながる。私もそうだった。好奇心を大事に持ち続けてほしい」 ○「好奇心を原動力に世間が必要とするものを引っ張りだしてきた」 ○「研究者には2つの側面が必要。1つは執着心。壁にぶつかってもすぐに諦めないこと。そして逆に柔らかい、能天気な面。それらのバランスをうまく取ることが必要だ。とがった部分と柔らかい部分ともいえる。 ○「失敗しないと絶対に成功はない」 ○「現代の若者が身につけるべき力は、観察力と洞察力だ。観察とは、例えば実験でこうなったと理解すること。洞察はなぜ、どういうメカニズムでそうなったのかを考えること。現代社会はインターネットのせいで情報過多の状況にある一方、若者は情報の中身 の洞察力を欠いている。ネット社会だからこそ、若者は洞察力を身に付けるべきだ。観 察力はいわば監視カメラで、洞察力は物が透けて見えるエックス線カメラ。2つのカメ ラをうまく使ってほしい」 子どもたちには「好奇心」「あきらめない心」「失敗は成功のもと」「観察力」「洞察力」これらを大切にし、毎日の学びに向かっていってほしい。 12月9日(月) 冷たい朝



これでも例年にくらべると暖かい冬だということで、今週半ばには再び寒さが緩み暖かい日になるということだ。三ツ渕小学校ではそうでもないが、インフルエンザも流行してきているようだ。健康管理に十分気をつけ、残り10日間の学校生活を元気に過ごして欲しい。 |
|