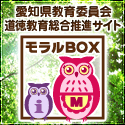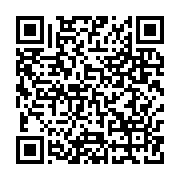|
最新更新日:2024/06/08 |
|
本日: 昨日:15 総数:156491 |
「第7回特別講座」で大人の学び(2) ●「統計データ」を活用するために 「統計データ」は、一見すると「ただの数字」の羅列です。 しかし、それらを「見やすく加工する」ことで、さまざまに活用することができます。 中学生でもよく知っている「円グラフ」「棒グラフ」「折れ線グラフ」などのグラフに加工することで、その数字の持つ意味が伝わりやすくなりますね。 企業は、自社の製品の優位性を消費者に伝えるために、広告などでよく「統計データ」を利用します。 新聞やテレビなどのメディアは、「世論調査」や「街頭アンケート」を行って、「国民の意見はこうです」という論調の根拠にします。 こうして出されるデータは、データを加工する側が「見せたいもの」を強調するつくりになっていることに注意する必要があります。 もとになる「数字」にうそはなくても、「見せたいもの」を誇張することで、見る人に誤った印象を与えることもあります。 ●「統計情報」にだまされないようにしよう 青山先生は、「統計情報」を見る時の注意点として、次のことを教えて下さいました。 ・グラフのつくりに注意しよう ・調査対象や方法の偏りに注意しよう ・「偶然」を「必然」だと思わせる置き換えに注意しよう 出されたデータを鵜呑みにするのではなく、「これは本当かな?」「これで何を伝えたいのかな?」と、データの根拠や意図に思いを巡らせることが大切ですね。 ********** 今回の講座では、実際に広告やニュースなどで使われた「データ」を使いながら、とてもわかりやすく「データのからくり」のついて教えていただきました。 「へぇ〜!」「なるほど!」という声がたくさん聞かれる、大人も子どももためになる講座になりました。 たくさんの3年生が参加してくれましたが、その中から一人でも二人でも、統計に興味を持ってくれた生徒さんがいたらうれしいですね。 今年度最後の「特別講座」も、親子で楽しく学べる講座になりました。 講師の青山先生、ありがとうございました! そして、参加して下さった皆様、ありがとうございました! 「第7回特別講座」で大人の学び(1) 昨年度に引き続き、愛知教育大学の青山和裕先生をお迎えして、「騙されない統計講座」で、親子で学びました。 【PTAの部屋】新しいこと始まりました!「第7回親子で学ぶ小牧中特別講座」 2/16 今回の講座で学んだことのまとめです。 ●「ビックデータ」って知っていますか? 最近、ニュースなどでも時々聞かれるようになった「ビックデータ」という言葉をご存じでしょうか? コンピューターやインターネットの普及に伴い、日常生活の中で、さまざまなことがこれらを利用して行われていますね。 その中でやり取りされる情報は、膨大な「データ」として蓄積されています。 これらのデータのことが、「ビックデータ」と呼ばれています。 例えば、「カーナビ」 今では、ほとんどの車に搭載され、皆さんも日常的に利用されていますよね。 カーナビは、GPSという衛星を使ったシステムで位置情報をやり取りして、経路を教えてくれたり、渋滞情報を教えてくれたりします。 そこでは多くの車からの情報がやり取りされるので、膨大なデータが集まっています。 そのデータを行政や企業が活用して、次のような取り組みが行われています。 1.「ある交差点では事故が多発する」という情報が得られた 2.どうしてそこでは事故が起きるのかを検証 3.原因になりそうなことがわかった「街路樹が邪魔で信号が見にくい」 4.それを改善した「木を伐採した」 5.事故の発生件数が減少した このような「ビックデータ」を活用した、さまざまな取り組みが、世界中で始まっています。 ●これが日本の「進むべき道」 日本は「自然資源」が豊富な国ではありません。 多くのものを輸入に頼っています。 そんな日本にも、世界に誇れる資源があります。それは「知的資源」です。 高い技術力を持つ日本の製品は、世界中でその品質が認められています。 その「知的資源」を活かすために、これからの時代に求められるのが、次のような「力量」なのです。 ・「ビックデータ」などの「統計データ」を活用する力 ・それらを活用して「新しいものを生み出す」力 これからの時代を生きる中学生の皆さんには、こうした「力量」を身につけてもらいたい、というのが青山先生のお話しでした。 新しいこと始まりました!「第7回親子で学ぶ小牧中特別講座」 すでに、学校HPで、校長先生が記事を発信して下さっています。 【小牧中HP】第7回親子で学ぶ小牧中特別講座(青山和裕先生) 2/16 今回は、すでに進路が決まっている3年生の生徒の皆さんが、多数参加してくれ、とても賑やかな講座になりました。 これには秘話があるのです。 実は、校長先生から「とても良い講座だから、よかったら参加してみないかい?一緒に学ぼう!」というお手紙が、生徒の皆さんに届いていたのです。 その想いに応えて、多数の生徒の皆さんが参加してくれた、というわけです。 生徒の皆さんは、きっと「来て良かったな〜」と思ってくれたことと思います。 校長先生、生徒の皆さん、本当にありがとうございました。 また、土曜日の夕方という忙しい時間の開催にも関わらず、小牧中の数学科の先生方も多数ご参加いただきました。 ありがとうございました。 親子で参加して下さった方、毎回参加して下さった方、今回初めて参加して下さった方、すべての皆さんに感謝しています。 そして、毎回準備など多岐にわたりお手伝いいただいた先生方、PTA役員の皆さん、本当にありがとうございました。 今回が、今年度最後の特別講座となりました。 来年度も、引き続き、楽しい講座をご用意して、皆さんのお越しをお待ちしています。 ぜひ、来年度の「特別講座」もよろしくお願いします。 「第6回特別講座」で大人の学び(2) ●親は、黙る ********** 「中学生時代は、大人への入り口です。この時期に身につけておかなければならないのは、『考える力』です」 「これは学校ではなく、家庭で身につけること。まず、親は知ったかぶりをしない。余計なことは言わない。黙るんです。自分で考えさせること」 「学校は、学ぶ姿勢を身につける場所。家庭は、考える姿勢を身につける場所」 ********** 私たちは、子どもが心配で、ついつい先回りして「こうしなさい」「それは違う」と言ってしまいがちですね。 しかし、中学生になったら、自分で考えさせることが大切だ、と教えて下さいました。 親が何でも教えてやらないで、わからないことは自分で調べさせること。「お母さんにはわからないから、あなたが調べて、わかったらお母さんにも教えてね」と、最初から突き放す。 皆さん、できますか? ●嘘も方便 ********** 「大人になったら、嘘の一つもつけなきゃダメですよ。嘘がつけなければ、大人の人間関係は築けない」 「でも、許される嘘と、そうでない嘘がありますね。許されない嘘は、『それは認めない』と毅然と言わなければなりませんよ」 ********** 「嘘も方便」といいますが、大人の世界には、相手を思いやる小さな嘘がたくさんありますね。 もちろん、ダメなものはダメ、ときちんと伝えなければいけません。 子どもは子どもなりに、「大人の事情」に戸惑い、反発しつつ、自分の中でバランスを取っていくものなのだと思います。 ●親は嫌われてナンボ ********** 「とにかく、親は嫌われてナンボですよ。親だからこうしないといけない、なんて決めつけることはないんです。石の上にも3年というでしょう。その3年が中学校の3年ですよ。どんどんケンカをすればいいんです」 「皆さんが自信を持つことです。あきらめたり、手を抜いたりしてはダメですよ。とにかく自信を持ってがんばって!」 ********** 最後は、力強くエールを送って下さいました。 角田先生は「親子の関係は、後になってみれば、笑い話にできるんです」とおっしゃっていました。 その真っ只中にいる私たちには、ほんとにそんな日がくるのだろうか・・・と苦しい日々が多いのですが、先生のこの言葉を信じて、石の上にも3年かじりついていきましょう。 今回も、人生の先輩として、子育ての先輩としての角田先生の言葉は、私たちの心にしっかり届きました。 角田先生、本当にありがとうございました! そして機会を作って下さった校長先生、ありがとうございました。 「第6回特別講座」で大人の学び(1) 角田明先生を講師に迎えた講座の模様は、「PTAの部屋」でもご紹介しています。 【PTAの部屋】新しいこと始まりました!「第6回特別講座」 2/3 角田明先生には、「第1回親子で学ぶ小牧中特別講座」でもお世話になりました。 いつも、心に深く染みわたるお話しで、何度お聞きしても、そのたびに新しい感動を感じることができます。 今回は「中学生を持つ親の資格」と題したお話しをして下さいました。 参加者のほとんどが、春にお子さんの中学校入学を控えている保護者の方々です。 角田先生は、そういう保護者の皆さんに向けて、優しく語りかけるようにお話しをされました。 角田先生の講演のまとめです。 ●大人が自信をなくしている ********** 「子どもが生まれて、時間がたてば、誰でも中学生の親になります」 ********** そうですね。中学生の親になることは特別なことではありません。しかし、子どもが、初めての中学生生活に不安を持つように、親も、初めての中学生の親生活に不安を持ちます。 ********** 「大人(親)が自信をなくしています」 「時代が、ものすごいスピードで変わっています。親は、自分がどうやって子育てをしていけばいいのかわからないんですね」 ********** 私たちが中学生だった頃とは、まるっきり時代が変わっています。自分の経験は、ほとんど役に立たないのです。 ●子育ての経験は特別なもの ********** 「困ったときには、自分の親に聞いてみなさい。でも、昔の話はあてにならないかもしれないよ」 「相談するのは、先生ですよ。それも、子どもが慕っている先生に相談しなさい。そして、先生自身が子育てを経験して、その厳しさを知っているなら、安心して相談できます」 ********** いくら毎日学校で子どもと接していたとしても、自ら子どもを育てる経験をしてみないとわからないことがある、ということですね。 それは、私たち保護者も経験してきましたね。子どもを持つ前と持った後では、子どもに対する意識が違ってきたと思います。 ●厳しい3年間になります ********** 「射的の的になるのが、中学生の親ですよ」 「子どもは親に向かってくるようになります。厳しい針のむしろに座らされるのが、中学校の3年間です」 「この時期の子どもは、大人の矛盾に抵抗してきます。大人批判をしてきますよ。その的に親がならなければならないんです」 「親に反抗しない子どもは、立派な大人になれないですよ。親と論争するエネルギーを持っていなければダメ。親は子どもと正面切ってケンカをすればいいんです」 ********** これからの3年間は、親にとっても、子どもにとっても、その後の人生のためにとても大切な時間だよ、と教えて下さっているのですね。 厳しい言葉が続きましたが、角田先生の言葉は、決して脅しのように響くものではなく、そういう覚悟がいるんだよ、その覚悟はできているかい?と問われているようで、聴衆の皆さんはきっとご自身の心を向き合ったと思います。 「第7回親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 <a href="<b>2/15(土)「第7回親子で学ぶ小牧中特別講座」が開催されます。</b> ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 (第7回特別講座チラシ) 今回の特別講座には、昨年度の「第2回親子で学ぶ夜の小牧中」に講師として来ていただいた青山和裕先生をお招きします。 昨年度の講座では、普段、何気なく見ているCMや広告には、意外な「統計のマジック」が隠されていることを、とてもわかりやすく教えていただき、大人にも子どもにも好評な講座となりました。 今回は、どのような「統計のヒミツ」を教えていただけるのか、とても楽しみですね。 大人も子どもも、どなたでも参加できますので、ぜひ皆さまお誘い合わせのうえ、小牧中学校にお越し下さい! 【日時、会場】 2/15(土)16:00〜17:30 多目的室 ※事前申し込みは不要。直接、小牧中学校へお越し下さい。 新しいこと始まりました!「第6回親子で学ぶ小牧中特別講座」 今回の講師は、昨年6月に「第1回」に登場していただいた角田明先生です。 当日は、新入生の保護者向けの「入学説明会」が開催され、その中で「中学生を持つ親の資格」という演題でお話をしていただきました。 来年度の新入生は270名を超える予定だそうです。 お子さんが初めて中学校に入学される保護者の方々は、いろいろな不安をお持ちだと思います。 そんな気持ちにこたえるように、角田先生は、校長先生としての経験や子育ての先輩として、厳しい言葉の中にも、あたたかい励ましのこもったお話をしてくださいました。 在校生の保護者も参加させていただきましたが、今、私たちは、親にとっても子どもにとっても、とても大切な中学校生活を過ごしているのだということに、改めて気づかせていただきました。 「PTAサロン」「リサイクル販売」「ミニミニ講演会」のあとの開催ということで、会場の準備はたいへんでしたが、PTA役員だけでなく、保健委員の皆さんにもお手伝いいただき、スムーズな設営ができました。 また、地域コーディネーターさんは、入学説明会のための受付などの準備にご尽力いただきました。 先生方ももちろんですが、多くの皆さんのご協力に感謝しています。 ありがとうございました。 「第6回 親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 2/3(月)「第6回親子で学ぶ小牧中特別講座」が開催されます。</b> ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 <swa:ContentLink type="doc" item="12937">(第6回特別講座チラシ)</swa:ContentLink> 今回の特別講座は、来年度入学予定の保護者向けの「入学説明会」の後半に「教育講演会」として開催されます。 講師には、「第1回親子で学ぶ小牧中特別講座」でお世話になった角田明先生をお招きします。 <a href="http://swa.komaki-aic.ed.jp/weblog/index.php?id=komaki_j_pta&type=1&column_id=102373&category_id=1507" target="_blank">【PTAの部屋】新しいこと始まりました!「第1回親子で学ぶ小牧中特別講座」 2013/6/14 角田先生には、昨年度の「入学説明会」でも講演をしていただき、参加された保護者の皆さんからは「もっと聞いていたかった」「先生の言葉がストンと胸に落ちて、とてもわかりやすかった」と、とても好評な感想が多く聞かれました。 今回も、多くの新入生の保護者が参加される予定ですが、在校生の保護者の皆さんにも参加していただくことができます。 ぜひお誘い合わせのうえ、ご参加ください。 なお、当日は「14:30〜入学説明」を実施し、そのまま「14:50〜特別講座」となります。 準備の都合上、在校生の保護者の方も、入学説明会の冒頭より会場に入っていただくことになりますのでご了承ください。 在校生保護者用の座席は、会場後方に準備する予定です。 【日時、会場】 2/3(日)14:50〜15:30 多目的ホール ※入学説明会内での開催になります(14:30〜15:30) 事前の申し込みは不要ですが、今回は「小牧中の保護者のみ」の参加とさせていただきます。 「第5回特別講座」で大人の学び 今回の「特別講座」は、NPOニワ里ねっとさんとの共催で、前半は小牧山城にてミニ講談と史跡解説が行われました。そして後半は小牧中学校にて旭堂南海さんの講談と間に校長先生との対談もあり、の豪華な内容でした。 講師の旭堂南海さんは、昨年11月の「第4回親子で学ぶ夜の小牧中学校」でも登場していただいたので、ご存じの方も多いと思います。 今回の演目は ・ 桶狭間の合戦 ・ 本能寺の変 の2本です。今年は織田信長が小牧山に城を築いてから450年の記念の年、ということで、織田信長にまつわる講談を披露して下さいました。 2本とも「超有名」な話しですので、知らない人はいないでしょう。 しかし、知っている話であっても、南海さんの講談をお聞きしていると、また改めて情景を思い描くことができて、とても楽しい時間でした。 ●思い浮かんだのは誰? 情景を思い浮かべる時、主人公である織田信長の顔も思い浮かんでくるのですが、皆さんはどんな顔が思い浮かぶでしょうか? 織田信長は、映画やドラマでいろいろな俳優が演じていますので、それぞれに好きな俳優の顔が思い浮かぶかもしれないですね。 ちなみに、私は、教科書でよく見る「肖像画」の信長像が思い浮かびました。 ●講談師は作家でもある 南海さんと校長先生の対談の中で、とても印象に残ったのは、3年に渡って1つの講談をされた、ということでした。 毎回最後は「次回に続く」という終わりになるのですが、それはそれは長い話しだったことと思います。 講談には長い物語もあるでしょうが、3年間に渡るとなると、元々の物語だけでは足りなくなってしまいますね。 そんな時は、物語を創作してしまうのだそうです。 講談は史実を元に物語が作られていますが、史実に忠実である必要はなく、脚色OKだそうです。 お客様の雰囲気に合わせて、その場で物語を変更することもあるそうです。 というわけで、講談師はただおしゃべりするだけではなくて、作家でもあるのですね。 ●イメージトレーニングが大切 講談は「しゃべる芸」ですから、相当な稽古を積んでいらっしゃると思いますよね。 南海さんも若手の頃はたくさん「しゃべる稽古」をされたと思いますが、ベテランとなった今では、ほとんどしゃべることはされず、もっぱら「イメージトレーニング」なんだそうです。 「しゃべる」となると、どこでもできる稽古ではありません。 家で練習していると、ご家族にうるさがられるそうですし、外でぶつぶつと練習していたら、ちょっと変な人と思われてしまいます。 そこで「イメージトレーニング」なんだそうです。これならどこでもできますね。 南海さんがイメージトレーニングで情景を思い浮かべながら練習していることが、きっと講談を聴く私たちにも伝わってくるんだなと思いました。 ********** 旭堂南海さん、今回も楽しい講談を聴かせていただきありがとうございました。 また、「NPOニワ里ネット」さんのイベントから、多数の皆さまにご参加いただきありがとうございました。  新しいこと始まりました!「第5回親子で学ぶ小牧中特別講座」 今回の講師は、昨年11月にもご来校いただいた旭堂南海さんです。 今回の特別講座は「NPOニワ里ねっと」さんとの共催ということで、歴史好き・講談好きのお客様に多数お越しいただきました。 今年は、織田信長が小牧山に城を築いた「小牧山城築城450年」という記念の年に当たるため、小牧市ではいろいろなイベントが開かれました。 それにちなみ、今回の演目は 「桶狭間の合戦」 「本能寺の変」 の2本でした。 いつものように、間に南海さんと校長先生の対談もあり、とても楽しい特別講座となりました。 対談の様子はこちら 準備から片付けまでお手伝いいただいたNPOの皆さん、PTA役員の皆さん、そして先生方、本当にありがとうございました。 「第5回親子で学ぶ小牧中特別講座」のお知らせ (【小牧中HP】講談のお勧め(11月30日親子で学ぶ特別講座) 11/27) 今回の特別講座の開催時間に変更がありましたので、改めてご案内します。 16:00 開場 16:30 開演 18:00 講演終了 事前の申込は不要です。 小牧中の保護者や生徒だけでなく、地域の方など、どなたでもご参加いただけます。 ぜひお誘い合わせのうえ、小牧中へお越し下さい! ●第5回特別講座チラシ(注意:チラシとは開催時間が変更になっています)は(【小牧中HP】講談のお勧め(11月30日親子で学ぶ特別講座) 11/27) 今回の特別講座の開催時間に変更がありましたので、改めてご案内します。 16:00 開場 16:30 開演 18:00 講演終了 事前の申込は不要です。 小牧中の保護者や生徒だけでなく、地域の方など、どなたでもご参加いただけます。 ぜひお誘い合わせのうえ、小牧中へお越し下さい! ●第5回特別講座チラシ(注意:チラシとは開催時間が変更になっています)はこちら 「第5回 親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 11/30(土)「第5回親子で学ぶ小牧中特別講座」が開催されます。</b> ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 <swa:ContentLink type="doc" item="12614">(第5回特別講座チラシ)</swa:ContentLink> 今回の講師には、講談師の旭堂南海師匠をお招きします。 南海師匠は、昨年度の「第4回親子で学ぶ夜の小牧中」で講師として講談を披露して下さいました。 その時の様子は、昨年度の「PTAの部屋」の記事をご参照下さい。 <a href="http://swa.komaki-aic.ed.jp/weblog/index.php?id=komaki_j_pta&type=1&column_id=88341&category_id=665" target="_blank">●【PTAの部屋】新しいことが始まりました 〜第4回夜の小牧中〜 2012/11/13 ●【PTAの部屋】「第4回夜の小牧中」で大人の学び(1) 2012/11/16 ●【PTAの部屋】「第4回夜の小牧中」で大人の学び(2) 2012/11/16 ●【PTAの部屋】「第4回夜の小牧中」で大人の学び(3)『最終回』 2012/11/16 今回は、「小牧山城築城450年」にちなんだ講談を披露して下さる予定です。 どんなお話しをしていただけるのか、とても楽しみですね。 また、チラシでご案内したとおり、「特別講座」の前に、NPOニワ里ねっと主催の「講談師とめぐる散策会」が小牧山にて開催されます。 興味のある方は「ニワ里ねっと事務局」(TEL:070-5365-1375)までお問い合わせ下さい。この散策会は、事前申し込みが必要になります。(13:30集合) 【日時、会場】 11/30(土)16:00〜17:30 多目的ホール どなたでもご参加いただけます。 事前の申込も不要ですので、お気軽にご参加ください。
|
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||