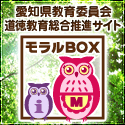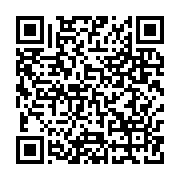|
最新更新日:2024/06/08 |
|
本日: 昨日:15 総数:156489 |
学び続ける校長先生 【小牧中HP】25年度第7回教師力アップセミナー(佐藤正寿先生)で学ぶ 2/16 小牧中の学校HPでは、このような「学んできました」という記事が、けっこうな回数で掲載されています。 驚くべきは、校長先生が自らこのようなセミナーや講演会などに参加され、常に学び続ける姿を見せて下さることです。 子どもたちに「継続的に学ぶ姿勢を身に付けさせたい」という思いをお持ちの校長先生は、日頃からその思いを発信されていますが、子どもたちにそれを求めるためには、自らが模範を示そうと考えていらっしゃるのですね。 先日最終回が終了した「親子で学ぶ小牧中特別講座」もそうですが、「愛マップ・プロジェクト」の活動でも、いつも校長先生は先頭に立って、積極的に参加してくださっています。 その背中を、多くの生徒たち、多くの保護者、そして多くの教職員の皆さんが見ています。 まさに、背中で教えて下さっているのですね。 今回のセミナーは、110名ほどの参加者があったそうです。 その中には、玉置校長先生以外にも、多くの校長先生が含まれているということを、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。 「自ら学ぶ校長先生」の姿は、私たち保護者にも多いに刺激を与えて下さいます。 そして、多くの先生方が同じように刺激を受けておられることと思います。 学校も保護者も、みんなで学びを楽しみながら「学びのあふれる小牧中学校」になっていくといいですね。 【関連記事】 ご紹介する学校HPは、すべて校長先生がセミナーに参加され、記事を発信されています。 たくさんの「自ら学ぶ校長先生」がいらっしゃいます! ●岩倉市立岩倉中学校HP 教師力アップセミナーに参加 2/16 ●大府市立東山小学校HP 教師力アップセミナー 2/16 ●知多市立新田小学校HP 2/16 教師力アップセミナー 2/16 新しいこと始まりました!「第7回親子で学ぶ小牧中特別講座」 すでに、学校HPで、校長先生が記事を発信して下さっています。 【小牧中HP】第7回親子で学ぶ小牧中特別講座(青山和裕先生) 2/16 今回は、すでに進路が決まっている3年生の生徒の皆さんが、多数参加してくれ、とても賑やかな講座になりました。 これには秘話があるのです。 実は、校長先生から「とても良い講座だから、よかったら参加してみないかい?一緒に学ぼう!」というお手紙が、生徒の皆さんに届いていたのです。 その想いに応えて、多数の生徒の皆さんが参加してくれた、というわけです。 生徒の皆さんは、きっと「来て良かったな〜」と思ってくれたことと思います。 校長先生、生徒の皆さん、本当にありがとうございました。 また、土曜日の夕方という忙しい時間の開催にも関わらず、小牧中の数学科の先生方も多数ご参加いただきました。 ありがとうございました。 親子で参加して下さった方、毎回参加して下さった方、今回初めて参加して下さった方、すべての皆さんに感謝しています。 そして、毎回準備など多岐にわたりお手伝いいただいた先生方、PTA役員の皆さん、本当にありがとうございました。 今回が、今年度最後の特別講座となりました。 来年度も、引き続き、楽しい講座をご用意して、皆さんのお越しをお待ちしています。 ぜひ、来年度の「特別講座」もよろしくお願いします。 【コーラス】2/9 活動報告  寒くて縮こまっていた体も、大きな声を出して練習するうちに、いつの間にかほぐれていきます。 今回も、ストレス発散の楽しい時間となりました。 次回の練習日は2/16(日)10:00〜12:00 音楽室です。 【生指】2/10 登校指導   寒い時期の朝の登校指導はたいへんですが、当番の委員さんには、ご協力いただきありがとうございました。 写真は、小牧警察署前の交差点での様子です。 愛狂亭三楽 独演会 in 小牧中 2014 今日のまくらは「落語鑑賞のあ・い・う・え・お」 普段は、敬老会などで落語を披露することが多い三楽さん(玉置校長先生)は、今日の観客が若い(!)お母さん方なので、とっても楽しいご様子。 賑やかな笑い声が響く中、流れるように、いつしか演目「子ほめ」へ。 人を上手にほめたらいいことあるよ、と教えられた男が、ご近所さんの赤ちゃんをほめまくって、ご馳走にありつこうとしますが、ほめ方をきちんと覚えていないので、いちいちピントがずれている、楽しいお話し。 たたみかけるように、スピードに乗った、三楽さんの落語に、参加者一同、たくさん笑わせていただきました。 早くも、来年度の全委員会でも、三楽さんの落語を聴かせていただくようにお願いをしておきました。 来年度の地区委員さん、ぜひご参加くださいね!(笑) 愛狂亭三楽さん(玉置校長先生)、本当にありがとうございました!  2/8 第6回全委員会 先ほどの専門委員会で出された意見を、各委員長さんから発表してもらいました。 来年度への提案が多く出されましたので、新しい委員長さんたちと相談しながら、PTA活動に反映させていきたいと思います。 ありがとうございました。 【広報】2/8 『専門委員会』 広報委員会 広報委員会では、年2回のPTA新聞発行に向けて、取材活動や編集会議を行ってきました。 現在も、3月の「PTA新聞101号」の発行に向けて、編集会議を重ねています。 委員会では、「今年度の反省」「来年度への提案」について話し合いました。 一年間ありがとうございました。 【生指】2/8 『専門委員会』 生徒指導委員会 生徒指導委員会では、毎月10日の登校指導や、ジュニア奉仕団の支援活動を行いました。 委員会では、「今年度の反省」「来年度への提案」を話し合いました。 一年間ありがとうございました。 【教養】2/8 『専門委員会』 教養委員会 教養委員会では、社会見学の他、教養講座、文化祭でのPTA作品展の活動を行いました。 委員会では「今年度の反省」「来年度への提案」について話し合いました。 一年間ありがとうございました。 【環境】2/8 『専門委員会』 環境委員会 環境委員の皆さんは、この前に「花植え作業」を行って下さいました。 委員会では「今年度の反省」「来年度への提案」を話し合いました。 一年間ありがとうございました。 【保健】2/8 『専門委員会』 保健委員会 あいにくの雪模様のため、参加者が少なかったのですが、「今年度の反省」「来年度への提案」について話し合いました。 保健委員会では、年3回の「制服等リサイクル販売」の活動を行いました。 「給食試食会」は、台風の影響で中止になってしまい、残念でした。 一年間ありがとうございました。 【総務】2/9 第5回総務委員会 総務委員会のあとに開催される「専門委員会」「全委員会」では、今年度最後となるため、各委員会で「活動の振り返り」「来年度に向けての改善提案」を話し合ってもらうように、各委員長さんに依頼しました。 また、PTA活動全般にわたっての見直しについても検討し、来年度の活動に向けた話し合いをしました。 総務委員会は、現メンバーで、4月のPTA総会の前に、もう一度開催されます。 総務委員の皆さん、どうぞよろしくお願いします。 【環境】2/8 花植え作業 凍えるほどの寒さでしたが、てきぱきと作業を進めていただき、短時間で終わることができました。 ありがとうございました。 来月の卒業式には、きれいな花を咲かせて、卒業生を迎えてくれると思います。 「第6回特別講座」で大人の学び(2) ●親は、黙る ********** 「中学生時代は、大人への入り口です。この時期に身につけておかなければならないのは、『考える力』です」 「これは学校ではなく、家庭で身につけること。まず、親は知ったかぶりをしない。余計なことは言わない。黙るんです。自分で考えさせること」 「学校は、学ぶ姿勢を身につける場所。家庭は、考える姿勢を身につける場所」 ********** 私たちは、子どもが心配で、ついつい先回りして「こうしなさい」「それは違う」と言ってしまいがちですね。 しかし、中学生になったら、自分で考えさせることが大切だ、と教えて下さいました。 親が何でも教えてやらないで、わからないことは自分で調べさせること。「お母さんにはわからないから、あなたが調べて、わかったらお母さんにも教えてね」と、最初から突き放す。 皆さん、できますか? ●嘘も方便 ********** 「大人になったら、嘘の一つもつけなきゃダメですよ。嘘がつけなければ、大人の人間関係は築けない」 「でも、許される嘘と、そうでない嘘がありますね。許されない嘘は、『それは認めない』と毅然と言わなければなりませんよ」 ********** 「嘘も方便」といいますが、大人の世界には、相手を思いやる小さな嘘がたくさんありますね。 もちろん、ダメなものはダメ、ときちんと伝えなければいけません。 子どもは子どもなりに、「大人の事情」に戸惑い、反発しつつ、自分の中でバランスを取っていくものなのだと思います。 ●親は嫌われてナンボ ********** 「とにかく、親は嫌われてナンボですよ。親だからこうしないといけない、なんて決めつけることはないんです。石の上にも3年というでしょう。その3年が中学校の3年ですよ。どんどんケンカをすればいいんです」 「皆さんが自信を持つことです。あきらめたり、手を抜いたりしてはダメですよ。とにかく自信を持ってがんばって!」 ********** 最後は、力強くエールを送って下さいました。 角田先生は「親子の関係は、後になってみれば、笑い話にできるんです」とおっしゃっていました。 その真っ只中にいる私たちには、ほんとにそんな日がくるのだろうか・・・と苦しい日々が多いのですが、先生のこの言葉を信じて、石の上にも3年かじりついていきましょう。 今回も、人生の先輩として、子育ての先輩としての角田先生の言葉は、私たちの心にしっかり届きました。 角田先生、本当にありがとうございました! そして機会を作って下さった校長先生、ありがとうございました。 「第6回特別講座」で大人の学び(1) 角田明先生を講師に迎えた講座の模様は、「PTAの部屋」でもご紹介しています。 【PTAの部屋】新しいこと始まりました!「第6回特別講座」 2/3 角田明先生には、「第1回親子で学ぶ小牧中特別講座」でもお世話になりました。 いつも、心に深く染みわたるお話しで、何度お聞きしても、そのたびに新しい感動を感じることができます。 今回は「中学生を持つ親の資格」と題したお話しをして下さいました。 参加者のほとんどが、春にお子さんの中学校入学を控えている保護者の方々です。 角田先生は、そういう保護者の皆さんに向けて、優しく語りかけるようにお話しをされました。 角田先生の講演のまとめです。 ●大人が自信をなくしている ********** 「子どもが生まれて、時間がたてば、誰でも中学生の親になります」 ********** そうですね。中学生の親になることは特別なことではありません。しかし、子どもが、初めての中学生生活に不安を持つように、親も、初めての中学生の親生活に不安を持ちます。 ********** 「大人(親)が自信をなくしています」 「時代が、ものすごいスピードで変わっています。親は、自分がどうやって子育てをしていけばいいのかわからないんですね」 ********** 私たちが中学生だった頃とは、まるっきり時代が変わっています。自分の経験は、ほとんど役に立たないのです。 ●子育ての経験は特別なもの ********** 「困ったときには、自分の親に聞いてみなさい。でも、昔の話はあてにならないかもしれないよ」 「相談するのは、先生ですよ。それも、子どもが慕っている先生に相談しなさい。そして、先生自身が子育てを経験して、その厳しさを知っているなら、安心して相談できます」 ********** いくら毎日学校で子どもと接していたとしても、自ら子どもを育てる経験をしてみないとわからないことがある、ということですね。 それは、私たち保護者も経験してきましたね。子どもを持つ前と持った後では、子どもに対する意識が違ってきたと思います。 ●厳しい3年間になります ********** 「射的の的になるのが、中学生の親ですよ」 「子どもは親に向かってくるようになります。厳しい針のむしろに座らされるのが、中学校の3年間です」 「この時期の子どもは、大人の矛盾に抵抗してきます。大人批判をしてきますよ。その的に親がならなければならないんです」 「親に反抗しない子どもは、立派な大人になれないですよ。親と論争するエネルギーを持っていなければダメ。親は子どもと正面切ってケンカをすればいいんです」 ********** これからの3年間は、親にとっても、子どもにとっても、その後の人生のためにとても大切な時間だよ、と教えて下さっているのですね。 厳しい言葉が続きましたが、角田先生の言葉は、決して脅しのように響くものではなく、そういう覚悟がいるんだよ、その覚悟はできているかい?と問われているようで、聴衆の皆さんはきっとご自身の心を向き合ったと思います。 2/3 ミニミニ講演会(2) 〜校長先生編〜 【校長先生編】 校長先生は、「教科書観の転換」について、お話しして下さいました。 保護者や、最近では塾の先生からも「教科書が終わっていないけど、大丈夫でしょうか?」という問い合わせがくるそうです。 教科書が分厚くなって、内容も増えていますから、ついつい心配になってしまうのですね。 教科書は、4年に一度、採択されるのだそうです。 ここで選ばれた教科書を子どもたちが使うことになります。 前回の採択のときから「教科書観の転換」つまり「教科書の作り方」が変わったそうです。 どういうことかというと、それまでのように教科書の内容は全部教えましょう、というスタンスではなく、子どもが「自分で勉強できるようなページ」を多く入れたのだそうです。 子どもの自学自習のためのページですから、当然授業では使いません。 このようなページが、実に4分の1ほどもあるのだそうです。 この「教科書観の転換」については、私たち保護者はもちろんですが、実は、学校の先生方にもあまり周知されていないそうです。 中にはご存じない先生もおられるのでしょうね。 「なんか、教科書分厚くなったよね・・・ハァ」とため息をつかれている先生もいたりして。 保護者の皆さんもご承知のとおり、教科書は税金で賄われていますから、子どもたちは無償で使うことができます。 ここに少々問題があって、「タダだから」「もらえるから」ということで、子どもたちが教科書を大切に扱ってくれないのですね。 教科書に使われる税金は、私たち保護者が払っているわけで、やはり子どもには大切に扱ってもらいたいものですね。 最近話題の「デジタル教科書」についても教えていただきました。 すでに、教師用のデジタル教科書は、小牧中にも導入されていて、先生方が授業で使っています。 文部科学省は、2020年までに、生徒に一人一台のタブレット端末を持たせて、そこにデジタル教科書を入れて使うことを決めているそうです。 あと6年後ですね。本当にそうなるでしょうか? 昨年、大変話題になった「反転授業」をご存じでしょうか? 佐賀県武雄市では、小中学校で一人一台のタブレット端末を導入して、「反転授業」をする取り組みを始めています。 「反転授業」というのは、まず明日習う内容を先生が講義しているところをビデオで撮影し、それを子どもたちの端末に入れます。 子どもたちは、それを家で見ながら「予習」をしてきます。 翌日、学校では、子どもたちが「予習」したところで、わからなかったことや疑問に思ったことをグループで話し合います。 このグループで話し合うことで、わからないところを教え合ったり、みんなで疑問を解決するために調べたりして、子ども同士が学び合うことを目的としているのです。 この取り組みは、まだ始まったばかりなので、今後どのように展開していくのか、関心を持って見ていきたいですね。 校長先生は、このように、いずれ子どもたちが端末を持ち、教科書がデジタル化していくことを見越して、運用上の問題なども教えて下さいました。 例えば、電源。 小牧中のように大規模校では、生徒の端末の充電をするだけの電源の確保は、とても難しい問題です。 また、端末へのデジタル教科書の入れ方について、それをインターネット経由で送信すればとても簡単なのですが、その場合は教科書の内容を簡単に訂正したりすることができますし、教科書の検定ができない可能性があります。 また、必要な設備などへの投資もしなければなりませんから、これまでのように教科書を無償で配布することができなくなるかもしれません。 しかし、世の中の流れとして(というか2020年にはやる、と文部科学省が言っているので)、子どもたちが端末を持つ時代は、すぐそこまできています。 それであれば、これまでの教科書のような雑な扱いではなく、子どもたちが大切に扱ってくれるようなツールにしたい、と校長先生はおっしゃいました。 校長先生のお話は、私たち保護者が知らないことばかりで、参加された皆さんは真剣に耳を傾けていました。 教科書の裏表紙などに「この教科書は税金で作られています」と、しっかり明記されているそうです。 皆さんも、一度お子さんの教科書を見てみて下さい。 今回も、学校のことがよくわかり、とても「ためになる話」を聞かせて下さいました。 校長先生、本当にありがとうございました! 2/3 ミニミニ講演会(1) 〜山崎先生編〜 今回ご登壇いただいたのは、山崎先生と玉置校長先生のお二人です。 山崎先生は、養護教諭ですから、普段は保健室にいらっしゃいます。 「保健室の先生」とよく言いますが、実際にどのようなお仕事をされているのか、興味がありますよね。 山崎先生に、「私の歩んできた道」として、養護教諭のお仕事についてたっぷりとお話しいただきました。 【山崎先生編】 まずは、養護教諭の各校への配置について教えて下さいました。 中学校の場合、生徒数が800名(801名以上)を超えると複数配置といって、2名の養護教諭が配置されるのだそうです。 小牧中学校の生徒数は800名を超えていますので、現在2名の養護教諭がいます。 また小学校の場合は、生徒数が850名(851名以上)を超えると複数配置となるそうです。 この50名の差は何なのか?よくわかりませんが、そのように規定されているそうです。 生徒の人数が多ければ、人数に比例して事務量も増えるわけなので、やはり大規模校の養護教諭はたいへんですね。 養護教諭の主な仕事は、皆さんご存じの「保健室の先生」ですが、具体的には「健康診断についての業務」「救急処置の業務」「保健指導の業務」があるそうです。 小牧中のように800名を超える大規模校では、生徒ひとりひとりの顔や名前を覚えるのは難しい、ということもおっしゃっていました。当然ですね。 年度の初めに「家庭調査票」や「健康調査票」を書いて学校へ提出しますが、これらの書類をきちんと書くことで、子どもの情報が学校でも正しく把握できます。 私たち保護者も、これらの書類の重要性を改めて考えたいですね。 山崎先生は、小牧中学校が、4校目の勤務校となるそうです。 まず最初に赴任した味岡小学校では、養護教諭が自分だけだったので、業務の内容がわからず大変苦労されたそうです。 養護教諭は特殊な業務を担っているので、校長先生や教頭先生にもどうしたらよいのかわかりません。 そこでお隣の味岡中学校の養護教諭の先生に、いつも相談されたそうです。周りの先生に支えられていたと感謝されていました。 次に赴任したのは、桃陵中学校。 ちょうど学校が荒れていた時期で、本当に大変な毎日だったそうです。 何年か後に、卒業生が立派に働いている姿を見かけて、当時から抱えていたいろいろな心の葛藤にうまく折り合いをつけて成長した姿に、心から「よかったなぁ」と思ったそうです。 そんな子どもたちの姿を見ていて、「甘えられる場所が学校だったのだと思います」とおっしゃっていました。子どもたちにとって、やはり学校は特別な場所のようです。 3校目は、篠岡中学校。 ここは、お隣の篠岡小学校の児童が、全員そろって入学してくる中学校です。 生徒数も少なく、生徒の顔もよく見える環境で、保健指導に力を入れられたそうです。 そういう環境から、大規模校への転勤だったので、やはり小牧中に来た当初は戸惑うことも多かったとのことでした。 山崎先生も、お二人のお子さんを持つお母さんです。 ですから、私たち保護者の気持ちをよくわかって下さっています。 「子どもというのは、親の思うようには育たない、ということは、私も実感しています」とおっしゃって、先生も私たちと同じなんだなぁと安心しました。 養護教諭として心がけていることは、子どもとの直接の関わりだけでなく、先生を通しての関わりも多いので、先生方とのコミュニケーションを取ることや、もちろん保護者とのコミュニケーションも大切にしたいとのことでした。 子どもは、たくさんの大人たちと関わり合いながら育てたいので、先生や保護者と連携していくことが大切だとおっしゃっていました。 自分ひとりでは何もできないことを知ることが大切で、早い段階で周りの大人と連携することが必要です、とご自身の経験から学ばれたことを教えていただきました。 子どもは、保健室に来たからといって、すぐに心を開くわけではありません。 ですから、いつも「受容的に聞く」ことを心がけでいます、と話して下さいました。 保健室は子どもにとってのオアシスではなく、子どもが最終的に帰る場所は「教室」なんです、という言葉に、山崎先生の子どもたちへの愛情を感じました。 私たちが知らない「養護教諭の世界」の一端に触れることができた、とても貴重な機会でした。 山崎先生、ありがとうございました。 これからも、小牧中の子どもたちが健康に楽しく学校生活が送れるように、よろしくお願いします! 「発信の鮮度」に想う   先生方は、研究会の会員として、劇にも参加されていましたし、会の運営にも関わっておられるので、たいへん忙しくされていました。 しかし、あとでそれぞれの学校HPを拝見していて、本当に驚きました。 多くの学校HPで「現地発信」がされているのです! 以前、「PTAの部屋」で、1年生のスキーの生活のときに、校長先生が現地からの発信をしてくださっていることを話題にしました。 【PTAの部屋】「現地からの発信」に想う 〜スキーの生活編〜 記事にあるように、現地から発信するためには、機器の準備が必要ですが、先生方はそれを自己負担でやられている場合がほとんどです。 さらに学校HPでは、記事の発信に、校長先生の承認が必要です。 今回ご紹介している学校HPでは、3校とも校長先生自らが発信されていますので、承認の手間がなく、スムーズに即時アップができるのです。 「情報」には、「鮮度」がありますね。 すぐに知りたい情報と、時間がたっても色あせない情報があります。 例えば、今開催中のオリンピックの結果は「すぐに知りたい情報」ですよね。 古くなってしまっては、あまり価値がありません。 一方、結果がわかっていたとしても、興味のある競技の試合は録画をして、あとでじっくり見たくなりますね。 時間が立っていても、試合の内容は価値があり、色あせるものではありません。 このように、情報にはさまざまな種類があり、それぞれに価値があると思うのです。 他校のHPで、このような「即アップ」がされていると、それを見た保護者は「どうしてうちの学校ではやってくれないのか!」と思われるかもしれません。 しかし、先に書いたように情報にはさまざまな種類がありますから、なんでもかんでも速攻でアップしなければならないということではなくて、その情報の特性に合わせてアップするタイミングを変えていけばいいのではないでしょうか。 ご紹介した3校のHPの記事は、ライブ中継のような「臨場感」を大切にした記事ですね。 速報としてお知らせすることで、見た人が「そこでどんなことが起きているのかな?」と関心を持ってくれます。 校長先生方が「現地からの発信」をして下さるのは、このように「見る人に関心を持ってほしい」という思いの表れではないかと感じています。 小牧中HPはもちろんですが、他校の学校HPからも、いろいろなことを学ばせていただいています。 保護者の皆さんも、ときどき他校の学校HPをのぞいて見て下さい。 きっと、何か「新しい発見」がありますよ。 【関連記事】 ●一宮市立木曽川中学校HP 2.09 フォーラム参加《校長室》 2/9 ※写真上段 ●一宮市立尾西第三中学校HP 2月9日(日)愛される学校づくりフォーラム 2/9 ※写真中段 ●一宮市立大和中学校HP 2月9日(日)<笑顔輝け大中>京都で行われた学習会に参加しました 2/9 ※写真下段 「愛される学校づくりフォーラム2014 in 京都」に参加 〜PTA編〜  この会は、玉置校長先生が参加されている「愛される学校づくり研究会」が年に一度主催し、全国から教員や教育関係者が集まるフォーラムです。 私たち保護者には、まったく馴染みのないフォーラムですが、今回、研究会のご厚意で、特別に参加の機会をいただきました。 【小牧中HP】「愛される学校づくりフォーラム2014 in 京都」に登壇 2/10 私たちは、午前の部「劇で語る!校務の情報化」に参加させていただきました。 ここでは、現在小牧市内の小中学校で導入されている「校務支援システム」について、それはどのようなシステムで、どのような利点があるのかということを、劇でわかりやすく提案されていました。 劇を演じるのは、研究会の先生方や、システム開発会社「EDUCOM」の社員の方々です。 皆さんお忙しいので、事前の稽古が満足にできず、直前リハーサルで初めて通し稽古を行ったそうですが、役者揃いで、そんなご苦労は全く感じさせないすばらしい劇でした。 私たちは「校務支援システム」を使う立場にはありませんが、今、学校現場ではどのようなことが問題になっていて、それらを解決するために、これはとても役立つシステムなんだな、ということがよくわかりました。 多くの学校で、この「校務支援システム」が導入されて、先生方の事務作業の負担が少しでも解消されるといいなと願っています。 会場では、小牧中から参加されていた梶田先生、伊藤陽平先生、尾関先生とお会いすることができました。 先生方が、わざわざ京都まで学びに来られていることを知り、その熱心な姿勢に、保護者としてもとても感心し、心強く思いました。 多くの先生方が、熱心に学ぼうとされていることは、保護者の皆さんにお伝えしたいことですし、子どもたちにも伝えていきたいと思います。 貴重な機会をいただき、ありがとうございました。 「新しい学校づくり推進事業プレゼンテーション会」を傍聴 この会の趣旨については、先日、学校HPに記事が掲載されました。 【小牧中HP】来年度と少し先まで考える 2/4 ほとんど知られていないことですが、小牧市でこのような事業が行われていて、このようなプレゼンテーション会が行われている、そしてそれを公開している、ということは驚くべきことです。 先の学校HPの記事にあるように、小牧市教育委員会が「できるだけ多くの市民に見てもらいたい」と考えておられるその姿勢に感心しました。 残念ながら、傍聴者は、学校関係者を除くと、小牧中のPTA2名と、その他に1〜2名いる程度でした。 各学校で、来年度取り組みたい事業の説明を行うプレゼンですから、学校の方針がよくわかります。 それぞれの学校の保護者の皆さんが、そういったことにも関心を持って傍聴されるといいなと思います。 小牧中がどのようなプレゼンテーションをしたか、という詳しい内容については、後日、学校HPに記事が掲載されると思いますので、その報告を待ちたいと思います。 自分の子どもが通う学校だけでなく、他校のプレゼンも見ることができ、他でやられているさまざまな取り組みについて知ることができたのは、とても勉強になりました。 このような貴重な機会に参加できるきっかけを作ってくださった校長先生にも感謝しています。 ありがとうございました。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||