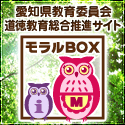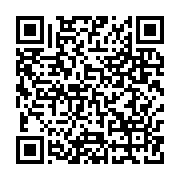|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:14 総数:156324 |
【コーラス】12/15 活動報告 急に寒くなり、体調を崩されてお休みのメンバーもいましたが、参加したメンバーで、楽しく活動しました。 会を重ねるごとに、チームワークが向上してきました。 これからの方向性を話し合い、「こんな曲が良いのでは?」といろいろなジャンルの曲を、みんなで試聴しました。 年内の活動は、今回が最後になります。 メンバーの皆さん、また来年、元気に会いましょう!  【広報】12/18 編集会議  どの行事の記事を掲載するか、記事の配置をどうするか、大まかなレイアウトを決めました。 記事に使う写真を選び、みんなで記事のコメントを考えました。 これからも編集会議を重ねて、3月の完成を目指します。 参加して下さった広報委員の皆さん、雨の中お越しいただきありがとうございました。 「学校給食のアレルギー対応」に想う〜再び〜 これは、文部科学省が公表した「2012年度の食物アレルギーのある子どもへの学校の対応状況の調査結果」に関する記事で、昨年度給食を実施した全国の公立小中学校から579校を抽出調査した結果、アレルギーのある子どもが対象の食物を取る「誤食」が5.9%で起こっていた、という内容でした。 忙しい保護者にとって、給食はとてもありがたいものですね。 そして、子どもたちにとっても、みんなで同じ給食を食べる経験は、栄養面からも重要ですし、とても大切な思い出になります。 しかし、昨今「食物アレルギー」の子どもが増え、昨年12月に調布市で起きた小学5年生の女の子の死亡事故のように、重大な結果になってしまう事例も増えています。 単に「除去食」を用意すればよい、という問題ではなく、子ども本人、保護者、担任の先生、栄養教諭、養護教諭など、さまざまな人が関わり、みんなで協力して対応していかなくてはならない問題です。 「除去食が確実に子どもへ渡るようにするにはどうするか」「おかわりはどうするか」「もしショック状態になってしまったらどう対応するのか」など、細かい対応が求められます。 ですから、給食実施校の中には、「うちの学校では対応できないので弁当にして下さい」という学校もあります。 小牧市では、本校の林先生が「今日の給食」の中で、折に触れ紹介してくださっているように「除去食対応」をしています。 専用の献立表を用意してくださっており、担任の先生に希望を伝えれば「アレルギー対応の献立表」をいただけるそうです。 これからもおそらく「食物アレルギー」の子どもは増えていくでしょうし、ますます個別の対応は難しくなってくると思います。 しかし、それでも「子どもたちにみんなと同じ給食を食べさせてあげたい」という先生方や学校の熱意で、さまざまな対応をしてくださっている小牧市教育委員会の姿勢に、保護者として感謝の思いでいっぱいです。 食物アレルギーのあるお子さんをお持ちの保護者の皆さんには切実な問題なのですが、普通に給食を食べている子どもたちとその保護者にとっては、あまり関心が持てない話題かもしれませんね。 ですが、おいしい給食を毎日食べられる幸せを実感するとともに、この機会に学校の食物アレルギー対策についても少し考えてみていただけるといいですね。 【関連記事】 【小牧中HP】小牧市の学校給食におけるアレルギー対応 2013/1/11 【PTAの部屋】「学校給食のアレルギー対応」に想う 2013/1/11 【生指】12/14 ジュニア奉仕団支援 アピタの出入り口は、場所によっては日陰になり、とても寒い一日でしたが、生徒の皆さんは寒さに負けず、大きな声で呼びかけをしていました。 生徒の呼びかけに応えて、たくさんの買い物客の皆さんが、募金に協力して下さいました。 私たちPTAも、生徒と一緒に立ち、呼びかけをしましたが、こうしてお手伝いができるのも健康に過ごしているからこそ、皆さんが協力して下さるからこそ、と感謝の気持ちでお手伝いをさせていただきました。 今回も3年生がたくさん参加してくれていて、「ボランティアが好きなんです」と少し照れながら話してくれる姿に、先日の中日新聞の記事が重なり、牧中生のことを誇らしく思いました。 <a href="12/14(土)生徒指導委員会では、ジュニア奉仕団の「歳末助け合い募金」のお手伝いを行いました。 アピタの出入り口は、場所によっては日陰になり、とても寒い一日でしたが、生徒の皆さんは寒さに負けず、大きな声で呼びかけをしていました。 生徒の呼びかけに応えて、たくさんの買い物客の皆さんが、募金に協力して下さいました。 私たちPTAも、生徒と一緒に立ち、呼びかけをしましたが、こうしてお手伝いができるのも健康に過ごしているからこそ、皆さんが協力して下さるからこそ、と感謝の気持ちでお手伝いをさせていただきました。 今回も3年生がたくさん参加してくれていて、「ボランティアが好きなんです」と少し照れながら話してくれる姿に、先日の中日新聞の記事が重なり、牧中生のことを誇らしく思いました。 <swa:ContentLink type="doc" item="12651">【小牧中HP】「役に立つ」って楽しい(平成25年11月25日中日新聞朝刊)</swa:ContentLink> 毎回ご協力いただく世話人の皆さま、担当の先生方、そして生徒指導委員の皆さま、参加してくれた生徒の皆さん、寒い中でしたが、本当にありがとうございました。  学校と家庭の連携 〜関心を持つ〜 (【小牧中HP】文部科学省で会議 12/12) 「文部科学省」というだけで、なんだかすごそうな響きですが、そこでの会議に委員として招へいされる玉置校長先生もタダ者ではない雰囲気ですね。 校長先生が参加されているおかげで、中央教育審議会が現在どのような会議をしているのか、という情報を知ることができるのは、実はとても幸運なことだと言えます。 「どうせ私たちには関係のないこと」とこれまでは全く興味や関心がなかった方も、ぜひ今後の会議の行方に注目してもらえるといいですね。 さて、先の記事の中で、学校と家庭や地域との連携についての記述がありました。 なんと、『学校・家庭・地域は相互の連携および協力に努めなさい』ということが「教育基本法」で規定されていたのですね。 子どもたちの教育のために三者が連携する必要がある、ということは、当たり前といえば当たり前の話ですが、現実にはそれぞれのバランスを保つことが難しい学校も多いのではないでしょうか。 小牧中学校では、昨年度から「新しいこと始めるよ!」ということで「親子講座」を開催したり、「愛マップ・プロジェクト」に取り組んだり、学校とPTAが協力して活動しています。 これらの活動は、PTAは役員を中心に、学校は校長先生や校務主任の先生が中心になって行っています。 スタッフの皆さんは、いつも楽しく活動できるように心配りをして下さり、感謝の気持ちでいっぱいです。 ただ、ここで一つお伝えしておきたいことがあります。 本来は、保護者の皆さんのすべてがPTA会員であり、そして先生方もPTA会員である、ということです。 残念ながら、「役員や地区委員じゃないから関係ないや」と思っていらっしゃる方が大半だと思いますが、皆さんお一人お一人がPTA会員なのです。 参加するしないに関わらず、「学校の様子」や「PTA活動の様子」に関心を持っていただけるといいなと思っています。 学校の様子は、学校HPでこまめに発信されていますし、PTA活動については「PTAの部屋」で随時発信しています。 これらのHPの情報を上手に活用していただき、学校のことやPTAのことに関心を持っていただければ、きっとさらに連携が深まるのではないでしょうか。 「三者が連携する」という言葉よりも「立場が違う大人たちが、一緒に楽しむ関係」になれるといいですね。 【図書ボラ】ボランティアさんからお礼のお手紙 (【PTAの部屋】【図書ボラ】12/4 読み聞かせ会 12/7) 図書ボランティアさんから、お礼のお手紙をいただきましたのでご紹介します。 ********** 今年のテーマは、学校の重点教育目標に掲げられている「命」にしました。 毎年、新しいことに挑戦しようと考え、今年は、生徒さんに「さて、何でしょうか?」と問いかけることをしてみました。 生徒の皆さんが どんな反応をするか、ちょっと心配しながらの企画でしたが、皆さんの反応がよくて、とても温かい気持ちで終えることができました。 聴き手が良いと、私たち話し手も、より上手くやれます。 あらためて、牧中の生徒さんたちの良さを実感しました。 先生方にも、機器等のことで お世話をかけたり、当日も参観してくださったりで、ありがたかったです。 我々メンバーも お役だち感一杯で 嬉しかったです。 取材して下さった 広報委員さんにも、「ありがとうございました。」と お伝えください。 本当にありがとうございました。 ********** 図書ボランティアの皆さんの中には、お子さんが卒業された後も、牧中生のために、積極的にボランティア活動をして下さっている方がたくさんいらっしゃいます。 お忙しい中でのボランティア活動には、いつも頭が下がります。 こちらこそ、ありがとうございました。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 【生指】12/10 登校指導  早朝から激しい雨が降り、どうなることかと心配しましたが、生徒の登校時間には雨があがっていました。 おかげで、無事に登校指導を行うことができました。 この日は、途中から校長先生も参加してくださったとのことで、当番の委員さんからは「校長先生がいると、子どもたちの挨拶が違いますね。さすがです」との感想が聞かれました。 このように、校長先生が気軽にPTAの活動に参加してくださるというのは、他校ではなかなかないことです。とてもありがたいことですね。 天候が不安定な中、朝早くから参加してくださった生徒指導委員の皆さん、当番の先生方、特別参加の校長先生、そして取材してくださった広報委員の皆さん、本当にありがとうございました。 ※写真上 小牧高校北大輪会館前 写真下 小牧警察署交差点 【おまけ】自転車の法律 自転車運転に関して、禁止されている行為は、意外とたくさんあります。 「知らずにやってしまっている」ことばかりだと思いますので、この機会に、ぜひ一度ご確認ください。 自転車に関する法律を、簡単にご紹介しておきます。 以下の行為は禁止されていますので、違反すると罰せられます。 ●二人乗り(ただし16歳以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させることは可) 2万円以下の罰金、または科料(1,000円以上10,000円以下) ●酒酔い運転 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金 ●夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金 ●手放し運転(傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む) 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ●歩行者妨害、歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもダメです) 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ●信号無視 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ●「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ●並進(2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金、科料 【関連記事】 ●政府広報オンライン 「知ってる?」「守ってる?」自転車利用の交通ルールとマナー ※画像は、警察庁HPのチラシを引用しています 自転車は「車」と同じ! ニュースなどでご存じの方も多いと思いますが、今回の改正により自転車への取り締まりが強化されています。 自転車通学の生徒だけでなく、中学生ならだれでも自転車に乗ると思いますが、危険な乗り方をしている子どもをよく見かけます。 「たかが自転車」と思わず、「自転車でも交通死亡事故を引き起こすことがある」ということを私たち保護者もしっかり認識して、子どもたちに注意させていきたいですね。 今回の改正道路交通法の主なポイントは、次の2点です。 -----*-----*-----*----- 1. 自転車は車道の左側を走行する。 自転車は「軽車両」となるので、歩道と車道の区別のあるところでは、原則として「車道」を通行します。 左側通行に限定されたため、右側を通行すると罰せられます。(3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金) 2. ブレーキのない自転車を検査することができる。 警察官が、ブレーキがない、あるいは不良の自転車を発見した場合、停止させて検査することができるようになりました。 命令に従わないと罰せられます。(5万円以下の罰金) -----*-----*-----*----- 「左側通行」については、これまでも言われてきたことですが、実際に車道を走行するとなると、車との距離が近すぎて危険な場所がたくさんありますね。 しかし法規制されましたので、できるだけ左端を走行するように、大人も子どもも気を付けていかなくてはなりません。 ご家庭で、ぜひ話題にしていただき、お子さんに「十分に気を付けて左側を走行するように」とお話ししていただけるといいですね。 ※画像は、警察庁HPのチラシを引用しています 【ランナーズ】12/8 小牧市民駅伝大会出場! すでに学校HPで、子どもたちの活躍ぶりは紹介されていますが、大人たちもがんばりました! 良いお天気に恵まれ、2チームで出場しましたが、どちらも無事に全員でたすきをつなぐことができました。 ランナーの皆さん、お疲れ様でした! 次の目標に向かって、また練習に汗を流しましょう。 そして、沿道でのたくさんの応援を、ありがとうございました。 大野前会長 おめでとうございます! 大野前会長、おめでとうございます! 大野前会長は、平成23年度・24年度の2年間に渡り、小牧市小中学校PTA連絡協議会の会長を務められ、平成24年度はそれ以外にも、愛日PTA連絡協議会、愛知県PTA連絡協議会の役員も合わせて務められました。 その功績を称え、愛知県PTA連絡協議会の推薦により、このたびの日本PTA全国協議会での表彰となりました。 たいへんお忙しい2年間でしたが、小牧中学校のためにご尽力いただきました。 この場をお借りして、心よりお礼とお祝いを申し上げます。 ありがとうございました! 【保健】求む!リサイクル品 学校公開日に開催する「制服等リサイクル販売」が毎回ご好評のため、リサイクル品が不足しています。 以前「PTAの部屋」でもお知らせしましたが、学校のご協力により、本日より個人懇談会の期間中、生徒昇降口に「リサイクル品回収箱」を設置していただけることになりました。 お子さんの成長に伴い使わなくなったもの、卒業して不用になったものなど、おうちに眠っている「牧中グッズ」がありましたら、学校へお越しの際に、ぜひご提供下さい! ご協力、よろしくお願いします。 【対象物品】 1. 制服(学生服、ズボン、セーラー服、スカート) 2. ジャージ、ハーフパンツ、コート、カーディガン 3. カバン、リュックサック 【提供方法】 1. ポケットの中身を確認し、空にして下さい。 2. クリーニングは必要ありません。ご家庭で洗濯をお願いします。 【図書ボラ】12/4 読み聞かせ会 12/4(水)に広報委員さんが取材に行って下さいましたのでご紹介します。 ********** 今回のテーマは「命」です。 「おじいちゃんがおばけになったわけ」を読んで下さいました。 死んでしまったおじいさんが、孫のエリックという男の子のもとへ、おばけとなって現れます。 「何かをしなくちゃいけないのに、それを忘れてしまった」おじいさんと一緒に、エリックが「何か」を探す、というお話でした。 図書ボランティアの皆さんの感情のこもった朗読に、胸がジーンと熱くなり、思わず涙が出てきてしまいました。 会場にいたすべての人々が見入ってしまうほど、とても素晴らしい読み聞かせでした。 ********** 図書ボランティアの皆さんは、子どもたちのために図書室の整備に力を入れて下さっています。 季節ごとに掲示物を変えたり、本の修繕や整理整頓など、いつも気を配って下さっています。 今回の「読み聞かせ会」は年一回の恒例行事ですが、子どもたちもとても楽しみにしています。 すてきな「読み聞かせ」をありがとうございました! お忙しい中取材して下さった広報委員さんもありがとうございました。 「第5回特別講座」で大人の学び 今回の「特別講座」は、NPOニワ里ねっとさんとの共催で、前半は小牧山城にてミニ講談と史跡解説が行われました。そして後半は小牧中学校にて旭堂南海さんの講談と間に校長先生との対談もあり、の豪華な内容でした。 講師の旭堂南海さんは、昨年11月の「第4回親子で学ぶ夜の小牧中学校」でも登場していただいたので、ご存じの方も多いと思います。 今回の演目は ・ 桶狭間の合戦 ・ 本能寺の変 の2本です。今年は織田信長が小牧山に城を築いてから450年の記念の年、ということで、織田信長にまつわる講談を披露して下さいました。 2本とも「超有名」な話しですので、知らない人はいないでしょう。 しかし、知っている話であっても、南海さんの講談をお聞きしていると、また改めて情景を思い描くことができて、とても楽しい時間でした。 ●思い浮かんだのは誰? 情景を思い浮かべる時、主人公である織田信長の顔も思い浮かんでくるのですが、皆さんはどんな顔が思い浮かぶでしょうか? 織田信長は、映画やドラマでいろいろな俳優が演じていますので、それぞれに好きな俳優の顔が思い浮かぶかもしれないですね。 ちなみに、私は、教科書でよく見る「肖像画」の信長像が思い浮かびました。 ●講談師は作家でもある 南海さんと校長先生の対談の中で、とても印象に残ったのは、3年に渡って1つの講談をされた、ということでした。 毎回最後は「次回に続く」という終わりになるのですが、それはそれは長い話しだったことと思います。 講談には長い物語もあるでしょうが、3年間に渡るとなると、元々の物語だけでは足りなくなってしまいますね。 そんな時は、物語を創作してしまうのだそうです。 講談は史実を元に物語が作られていますが、史実に忠実である必要はなく、脚色OKだそうです。 お客様の雰囲気に合わせて、その場で物語を変更することもあるそうです。 というわけで、講談師はただおしゃべりするだけではなくて、作家でもあるのですね。 ●イメージトレーニングが大切 講談は「しゃべる芸」ですから、相当な稽古を積んでいらっしゃると思いますよね。 南海さんも若手の頃はたくさん「しゃべる稽古」をされたと思いますが、ベテランとなった今では、ほとんどしゃべることはされず、もっぱら「イメージトレーニング」なんだそうです。 「しゃべる」となると、どこでもできる稽古ではありません。 家で練習していると、ご家族にうるさがられるそうですし、外でぶつぶつと練習していたら、ちょっと変な人と思われてしまいます。 そこで「イメージトレーニング」なんだそうです。これならどこでもできますね。 南海さんがイメージトレーニングで情景を思い浮かべながら練習していることが、きっと講談を聴く私たちにも伝わってくるんだなと思いました。 ********** 旭堂南海さん、今回も楽しい講談を聴かせていただきありがとうございました。 また、「NPOニワ里ネット」さんのイベントから、多数の皆さまにご参加いただきありがとうございました。  「スペシャル・道徳授業」に想う(3) ●好きなことならがんばれる 向さんが「動物介在福祉事業」を立ち上げられるまでには、相当の努力が必要でした。 闘病のために小学校は3年間しか通えなかったため、学力も体力もなかったそうです。 しかし「動物が関わる福祉をやりたい」という希望を持ったことで、それに関する英語の文献を読みたくて、ローマ字も書けなかった向少年は辞書を片手に英語の勉強に取り組んだそうです。 そういう努力を続けることで、今の向さんがいるのです。 「好きなこと」「やりたいこと」であれば、一生懸命努力することができる、ということを教えていただきました。 ●「勉強」ではなく「学ぶ」 向さんは、「自分がやりたいと思ったことだったので、自分から学ぶことができた」とおっしゃいました。 よく「勉強する」と言う言葉を使いますが、向さんは「勉強というのは、誰かに教えてもらうこと。自分から『知りたい』と思ったことを知る努力は『学ぶ』ということだ」とおっしゃって、自ら学ぶことの大切さを教えて下さいました。 保護者として、またPTA役員として、学校と関わっていて感じていること。 それは「小牧中には『学び』があふれている」ということです。 子どもたちは「学び合う学び」で、日々の授業の中でお互いに学び合っています。 先生方は「鍛える学び合う学び」で、授業研究などでお互いに学び合っています。 そして私たち保護者も「親子で学ぶ小牧中特別講座」や「しゃべり場」などで学んでいます。 また「注文ボランティア」や「ジュニア奉仕団」「愛マップ」の活動では、地域の方々からも学んでいますね。 このように、子どもたちだけでなく、私たち大人も楽しく学び合える、素晴らしい環境にあることを、改めて実感できた「スペシャル・道徳授業」でした。 校長先生はじめ小牧中の先生方、一緒に参加させてくれた2年4組の生徒の皆さん、そしてスペシャルゲストの向さん、本当にありがとうございました。 「スペシャル・道徳授業」に想う(2) ●「代わってあげたい」という親心 向さんのご両親が、闘病中に「代わってあげたい」と言われたひと言は、親なら誰もが思うことですね。 当時はよく意味がわからなかったが、自分が親となり、その時の両親の言葉が「自分が代わりに死んでもいい」という気持ちだったのだとわかった、と向さんはおっしゃいました。 その立場になってみて初めてわかること、というのが、世の中にはたくさんあります。 子どもたちには、今はピンとこないかもしれないけれど、いつかわかる時が来ると信じて、少々耳の痛いことも厳しいことも、やはり伝えていかなくてはいけないなと思いました。 先の記事で書いた「親としてどのように支えるか」を発表していて痛切に感じたことですが、ぜひ子どもたちへ伝えたい「親から子どもたちへのメッセージ」としてご紹介します。 ********** 子どもたちへ あなたの親は、誰よりも何よりもあなたのことをかけがえのない存在だと心から思っています。 口に出しては言わないかもしれないけれど、必ずそう思っています。 だから、どうかお願いです。 つらい時、苦しい時、一人で悩まず、あなたの親に話して下さい。 「親に心配をかけたくない」という気遣いは無用です。 あなたが一人で苦しんでいることの方が、よっぽど心配なのです。 あなたの親は、いつでもあなたに寄り添っていてくれますよ。 ********** ●「がんばって」よりも「がんばったね」 授業の中で、「がんばって」という言葉が出てきました。 私たち親は、あまり意識せずに、毎日「がんばって!」と子どもを励ましていますね。 向さんも闘病中、何万回も「がんばって」と言われてきたそうです。 しかし、この「がんばって」という言葉、言われた側の状況によっては、とても無責任に聞こえることがある、という向さんの言葉に、私たちはハッとしました。 向さんはさらに続けて、「がんばって」とは言われるけど「がんばったね」とは言ってもらえない、とおっしゃいました。 たとえ失敗したとしても、子どもは十分に「がんばった」のですから、「よくがんばったね」とがんばりを認めてあげる一言の大切さを教えてもらいました。 「スペシャル・道徳授業」に想う(1) 校長先生が進められた道徳授業の内容は、「人権集会」で向さんの半生をお聞きした上での、次の2点でした。 ・ いじめに負けずに登校できたのは、友人や両親の支えであったとのことだが、それはどのような支えだったのかを想像する ・ なぜ「動物介在福祉事業」を思い立ったのか 授業の様子や、授業の中で感じたことをご紹介します。 ●友人の支えについて想像する まず生徒の皆さんに「自分だったら、向少年にどのような言葉をかけるか」を想像してもらい、発表してもらいました。 いろいろな意見が出ましたが、中には、自分も入院の経験があり、その時に友だちにかけてもらった言葉がうれしかった、という自分の経験を話す生徒もいました。 「想像してみる」ということは、とても大切なことです。 これまでに経験したことのない状況なので、どういう言葉をかけたらいいのかわからないのが普通だと思います。 しかし、生徒の皆さんは、その場面を想像して、真剣に考えていました。 つらく苦しい思いをしている友だちにかけるべき言葉には、正解はありません。 それぞれが、一生懸命相手の立場になって考え、もし自分がその場にいたらと考えて発する言葉は、それぞれに思いのこもったステキな言葉になると思います。 生徒の皆さんが発表してくれたすべての言葉が、とてもステキな言葉でした。 ●両親の支えについて想像する 今回は、PTA役員も数名授業に参加させていただきました。 せっかくお母さん方が参加しているので、という校長先生の発案で、私たちも親として「向少年の両親はどのように支えたか」ということを想像して、発表させていただきました。 「我が子がいじめられている」という状況は厳しいものなので、想像することがとても難しかったです。 それでも一生懸命考えた「お母さんからの言葉」をそれぞれに発表させていただき、生徒の皆さんも真剣に聞いてくれました。 子どもは子どもなりに、「自分のお母さんならこう言うだろうか」と想像しながら、私たちの発表を聞いてくれたことと思います。 授業を通して、「親の想い」を伝えられたことは、私たちにとってもすばらしい経験になりましたし、子どもたちにとっても、自分の親ではない、他人のお母さんの想いを聞くことで、親というのはこんなふうに考えているものなんだ、ということに気付いてくれたのではないかと思っています。 【コーラス】12/1 活動報告   今回から、初めてのゴスペルに挑戦! まずは、ストレッチをして、体をほぐしてから声を出し始めます。 「アメージング・グレース」を練習していますが、今はまだ歌詞を付けることより、音を追っていく状態です。 楽しく練習することが一番ですね。 「人権集会」に想う 校長先生のご厚意で、保護者にも公開して下さるということでしたので、PTA役員数名で参加してきました。 集会では、昨日「対談集会」とご紹介したように、「NPO Animal-funfairわんとほーむ」の向さんをお迎えして、校長先生と対談をしながら、向さんのこれまでの人生を語っていただきました。 お話しいただいた内容は、すでに学校HPに記事がアップされていますので、こちらをご覧ください。 (【小牧中HP】人権集会(向さんとの対談) 12/3) とてもつらく苦しい闘病生活を経験し、学校ではいじめにも遭いながらも、決してくじけることなく、ひねくれることもなく、将来の夢をしっかり持って、それに向かって努力し続けてきた向さんのお話しは、親として胸が詰まる想いもありましたが、経験に裏付けられた「力強いメッセージ」を感じることができて、とても感動しました。 私たちは、体育館の一番後ろから集会の様子を見せていただきました。 正直言って、一番後ろからでは、舞台上の向さんや校長先生の姿、スライドの画面などは、ほとんど見えません。 しかし、上の写真を見て下さい。 子どもたちは、しっかりと顔を上げて正面を向いて、一生懸命話を聴いているのです。 体育館の床に座っていると足元から冷えてきますが、みんなじっと動かずに前を見ているのです。 その姿を後ろから見て、校長先生が日頃からおっしゃっている「ABCDの原則」がしっかりできるというのは、こういうことなんだな、と改めて教えられましたし、牧中生は本当にすばらしいな!とうれしく思いました。 子どもたちは、私たち保護者とは違う想いで、向さんのお話しを聴いたことと思います。 ぜひご家庭で、今日の「人権集会」のことを話題にしてみて下さい。 そして、子どもたちの「想い」を聴いてあげて下さい。 「かけがえのない命」について親子で考えるきっかけになるといいですね。 新しいこと始まりました!「第5回親子で学ぶ小牧中特別講座」 今回の講師は、昨年11月にもご来校いただいた旭堂南海さんです。 今回の特別講座は「NPOニワ里ねっと」さんとの共催ということで、歴史好き・講談好きのお客様に多数お越しいただきました。 今年は、織田信長が小牧山に城を築いた「小牧山城築城450年」という記念の年に当たるため、小牧市ではいろいろなイベントが開かれました。 それにちなみ、今回の演目は 「桶狭間の合戦」 「本能寺の変」 の2本でした。 いつものように、間に南海さんと校長先生の対談もあり、とても楽しい特別講座となりました。 対談の様子はこちら 準備から片付けまでお手伝いいただいたNPOの皆さん、PTA役員の皆さん、そして先生方、本当にありがとうございました。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||