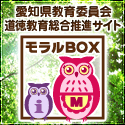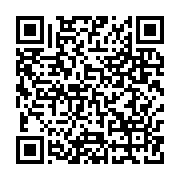10/31(木)の「第4回親子で学ぶ小牧中特別講座」のまとめの第2回です。
●教育とは
ここで、城下先生は、大変難しい質問をされました。
「教育とはなんでしょう?」
城下先生が考える「教育」とは、「学習の場」である、ということでした。
では「学習」とは?
城下先生は「何かができるようになること」とおっしゃいました。
ですから、「防災教育」は「学習」して「防災対策ができるようになること」というわけです。
では、「どうして学習するのか?」という問いに対して、学校の先生方はいつもどのように答えているのか、という話題になり、ご参加いただいた小牧中の先生方は次のように答えました。
「将来の選択肢を増やすため」
「自分の可能性を広げるため」
さすが、先生方は答え慣れていらっしゃいます。
子どもたちが、将来生きていく上で「学習(勉強)は役に立つよ」というメッセージを、きちんと伝えられています。
さらに城下先生はおっしゃいました。
「自分は、その問いに『世界に影響を与えるため』と答えます」
世界とは、文字どおりの世界中という意味もありますが、自分の身の回りにある「小さな世界」も含まれます。
家族、友だち、地域なども、それぞれが「小さな世界」ですね。
城下先生がおっしゃりたいのは「自分が知っていることが、世界の役に立ったという実感や、役に立てるという確信を持てることが、学習する理由だ」ということで、それが「生きる喜び」につながり、「学習する意欲」につながるというお話をして下さいました。
●再び「自助」の意味を考える
「教育」についての深いお話しの後で、城下先生は、再び「自助」について話題を戻されました。
「自分のこと」というのは、一生懸命やっても、誰かから感謝されるようなことではありません。
「感謝される喜び」が得られない「自分のこと(自助)」はどうしても後回しになりがちなのだそうです。
「自助」というと、多くは「個人の問題」と捉えられがちですが、もともと「自助」には「専門家にも正解がわからない問題があります。それを皆さん、一緒に考えて下さい」という意味があるそうです。
正解があるわけではないので「自分で意思決定しなければならない」という状況のことですね。
ですから、状況に応じて、地域ごと・学校ごと・家族ごとなど、それぞれの「ルール」を冷静に決めておくことが必要だと教えていただきました。