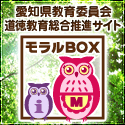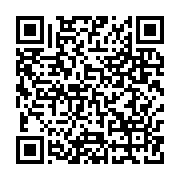|
最新更新日:2024/06/08 |
|
本日: 昨日:15 総数:156489 |
【生指】9/10 登校指導   今回の指導場所は、以下の3地点です。 ・小牧一丁目東交差点(写真上) ・山北橋(写真中) ・小牧五丁目交差点(写真下) 広報委員さんが取材をして下さいましたので、コメントをご紹介します。 ********** 9月に入り、登校時間中は爽やかな気候になってきました。 歩きながらお友達との会話も弾んでいるようですね。 弾みすぎて、他の通行人の方たちのご迷惑にならないよう、これからも登校してもらいたいと思います。 当番の保護者の皆さま、先生方、朝のお忙しい時間に参加していただいて、ありがとうございました。 ********** 取材して下さった広報委員の皆さん、登校指導に参加していただいた生徒指導委員の皆さん、そして当番の先生方、どうもありがとうございました。 【市P連】9/7 父母と教師のつどい 市内の小中学校から、たくさんの保護者の皆さんと先生方が参加され、講演会では、スクールカウンセラーの竹内成彦さんから、「子どもを育てるとっておきのメッセージ」と題したお話しをお聞きしました。 広報委員さんが取材して下さったので、そのコメントをご紹介します。 ********** 9月7日(土)東部市民センターで「父母と教師のつどい」に参加して来ました。 今回は講師に竹内成彦さん(心理カウンセラー)をお招きしての講演で、「子どもを育てるとっておきのメッセージ」と題して、御自身の経験談を混じえてユーモアたっぷりに話されたので、あっという間に時間は過ぎていきました。 先生の著書の抜粋で 「…子どもは無条件に親を愛してくれます。なんてありがたいことなのかと思います。…いつから親は、子どもを条件付けで愛するようになったのでしょう。人を無条件で愛することの大切さを教えてくれた子どもに、私は深く感謝しています。そして私は、そんな子どもを強く尊敬しています。」 とありました。 子どもも思春期にはいり、親も日常に追われ、忘れかけていた子どもの優しさや笑顔を、もう一度よく見て、聴いて、認め、時にはお互い照れ臭くなってきたスキンシップを計って、声をかけてみようかな…と振り返させられ、最後には穏やかな気持ちにさせて頂けた会でした。 大変勉強になり、機会があれば、たくさんの方に触れて頂きたい内容でした。 ********** 取材をしてくださった広報委員の皆さん、ありがとうございました。  【コーラス】活動日のお知らせ 以下をご覧いただき、ぜひご参加ください。 見学、飛び入り大歓迎です! 【9月の活動日】 9/15(日) 9/22(日) 10:00〜12:00 音楽室にて 大人は尊敬できますか? ある新聞の調査によると、今の子どもたちは、大人をこんなふうに見ているらしいのです。 「あなたは教師を尊敬しますか」 平均85% 日本21% 「あなたは親を尊敬しますか」 平均95% 日本25% 「あなたは自分に価値があると思いますか」 中国90% 日本35% 出典元が不明なので詳細はわかりませんが、おおざっぱに言って「日本の大人は、子どもに尊敬されていない」ということだと思います。 また、子どもたちがあまり自己肯定感を持っていないことも気になります。 「尊敬」というのは、「尊敬しなさい」と押し付けるものではありませんから、私たち大人がよく考えて、自然に子どもに「尊敬してもらえる」ような大人になるしかありません。 自分は尊敬されるに値する立派な人間だ、と自負できるような大人ばかりでないことはよくわかっていますが、やはり「大人が尊敬されていない」というのは、少しさみしい思いがします。 だからと言って、子ども受けを狙って、気に入ってもらえるようなことばかりする必要はありません。 きっと、そんな大人の心の中を、子どもは見抜いてしまうでしょう。 「好かれること」と「尊敬されること」は違いますよね。 やはり、子どもにとっては耳の痛いことも、口を酸っぱくして言い続けるのが、大人の役目なのではないでしょうか。 そして、やはり子どもには「自己肯定感」を持たせたいですね。 この「自己肯定感」は、親から子どもにプレゼントしてあげられますよ。 親は子どもに、ついつい小言ばかり言ってしまいますが、そればかりではなく、「あなたがいてくれてうれしい」「あなたは大切な家族の一員」「あなたのことが大好き」と伝え続けていきたいですね。 【関連記事】 ●佐藤正寿先生ブログ(地域のよさ・日本のよさを伝える授業)「あなたは教師を尊敬しますか?」 9/6 「2020年東京オリンピック」に想う(2) 皆さんの心をワクワクさせる、うれしいニュースであることは疑いようもありません。 しかし、浮かれてばかりもいられないな、という気持ちになるインタビューを見ました。 東日本大震災で被災した人々のインタビューでした。 「そりゃめでたいことだけど、そちらの方ばかりに気が取られて、復興が遅れないか心配」 「放射能や汚染水は大丈夫って総理は言うけど、自分たちはいつまでたっても自宅には戻れない」 「7年後なんて、私たちは、明日のこともわからないのに」 まもなく、9/11(水)で、東日本大震災から2年半という節目の日を迎えます。 今なお、不自由で不安な思いを抱えて生活されている人々がたくさんいること、行方不明の親族を捜し続ける人がたくさんいること・・・忘れてはいけませんね。 「忘れられるのが一番こわい」と言った被災地の人々の心を、忘れてはいけませんね。 おそらく9/11は、新聞やテレビでも「震災特集」のような記事が出ると思います。 せめて、このような節目の時だけでも、それらの記事に触れ、被災地に思いを馳せたいですね。 オリンピックの盛り上がりと同様に、国民が一丸となって、被災地の復興に力を注げる日本であることを願っています。 ※写真は、今年3月にまなび創造館で開催された「震災パネル展示」の様子です。 (【PTAの部屋】あれから2年「忘れないで」 3/6) 「2020年東京オリンピック」に想う(1) 開催地決定の瞬間を見るために夜更かしした、という方もたくさんいらっしゃるでしょう。 大人も子どもも、「7年後、自分は何歳になっているかな?」「オリンピックの観戦に行けるかな?」と、ワクワクした気分になるうれしいニュースでした。 7年後と言えば、今の中学生や高校生たちが、ちょうど主力選手になっている頃ですね。 子どもたちが、「東京オリンピックに出場したい!」と、がんばる原動力になるといいですね。 最終プレゼンテーションをテレビで見ました。 どなたも、堂々と感情をこめて、とても立派なスピーチをされていたことに、感動しました。 ご覧になった方はご存じだと思いますが、すべて英語(一部フランス語もあり)のスピーチです。 すばらしかったのは、誰一人として、手元に原稿を持たず、しっかり顔を上げて聴衆の皆さんの顔を見ながらお話しされたことです。 プロンプター(透明な板に、話し手には見えるように、原稿を投影する装置)は設置されていましたが、それを見ながらスピーチされている人はいないようでした。 以前、小牧中HPで、生徒会役員の生徒が「ノー原稿」で立派に発表をした、という記事が掲載されました。 このように、聴衆の顔を見ながら、堂々とスピーチすることは、話し手の考えや想いが、より皆さんに伝わるということですね。 今回のオリンピックの最終プレゼンテーションを見ながら、すばらしい小牧中の生徒の皆さんのことを、改めてとても誇りに思いました。 (【小牧中HP】小牧中集会での当たり前のレベル 5/1) さて、このプレゼンテーションの最後では、各国のIOC委員からの質問に答える質疑応答の場面もありました。 ここでも、英語での質疑応答が行われました。 あらかじめ用意した原稿があるわけではない突発的な質問に、その場で答えるのは日本語でも難しいことですが、しっかり英語で対応されている招致委員の皆さん方はすばらしいですね。(原発関連の質問に対して、安倍総理が日本語で回答していたのは仕方ないでしょうが) やはり、世界で活躍するためには、英語などの外国語を身につける必要があるなと感じました。 7年後、東京でオリンピックが開催されます。 先ほども書きましたが、今の中学生や高校生は、その頃20代前半になっています。 競技者として参加できるのは、ほんの一握りの人たちですが、それ以外にもボランティアなどで参加することもできます。 子どもたちには、プレゼンテーションで滝川クリステルさんが強調していた「おもてなし」の心を持って、海外から訪れるたくさんの人々のために何かしらお手伝いができるように、ぜひ外国語の勉強にも力を入れてほしいなと願っています。 ※写真上:中日新聞の号外/写真下:ノー原稿で立派に発表する牧中生  【保健】リサイクル品を求めています! 毎回ご好評のため、現在、リサイクル品が不足しています。 お子さんの成長に伴い使わなくなったもの、卒業して不用になったものなど、おうちに眠っている「牧中グッズ」を、ぜひご提供下さい。 ご協力、よろしくお願いします。 【対象物品】 1. 制服(学生服、ズボン、セーラー服、スカート) 2. ジャージ、ハーフパンツ、コート、カーディガン 3. カバン、リュックサック 【提供方法】 1. ポケットの中身を確認し、空にして下さい。 2. クリーニングは必要ありません。ご家庭で洗濯をお願いします。 3. 学校に直接お持ち下さい。お子さんを通じてでもかまいません。 【環境】8/31 除草作業 夏の間に伸び放題になっていた雑草退治をがんばりました。 9/21(土)の体育大会を前に、すっきりした校舎周りや運動場になりました。 参加してくださった環境委員の皆さま、ありがとうございました。 ※当日の写真がないため、活動の様子をお伝えできず、ごめんなさい。 8/31 校長先生の「学校がよくわかる話・2」(3)『最終回』 ●「『鍛える』学び合う学び」の実現に向けて 本当は、すべての授業が、このような「学び合う学び」の姿になることが望ましいのでしょう。 しかし、授業の内容によっては、先生が教え込まなければいけない内容もあるでしょうし、一斉授業の方がよい場合もあると思います。 それでも、小牧中ではできる限り「学び合う学び」の授業ができるように、「鍛える」というキーワードをつけて取り組んでいます。 「鍛える」のは子どもだけではありません。先生方も、熱心に勉強されています。 小牧中HPでは「学び合う学び」というコーナーを設けて、目指す姿をわかりやすく紹介してくださっています。 この情報発信は、私たち保護者だけに向けたものではないのです。 子どもたちには「このような学びをしているクラスや仲間がいるよ」というメッセージとして、また先生方には、他クラスの授業風景を見せることで、自分の授業の参考にしてもらおう、という狙いもあるそうなのです。 そのような深い思慮の元に発信されているHP、本当にありがたいことですね。 保護者にとってわかりやすい学校の様子、ということにとどまらず、子どもたちにも先生方にも、きっとすばらしい影響を与えていることでしょう。 もし、お子さんのクラスの風景が掲載されていたら「どんな授業だったの?」と、ぜひご家庭で話題にしてみてくださいね。 学校を知る、よいきっかけになるといいですね。 今回、「校長先生の学校がよくわかる話」をお聞きして、小牧中学校が取り組んでいる「学び合う学び」が、何を目指しているのか、ということがよくわかりました。 このような「教育方針」について、校長先生から直接お話しをお聞きする機会は、めったにないことです。 直接お話しをお聞きすることで、学校の現状や目指していることが私たち保護者にもよくわかり、信頼感が増しました。 お忙しい中で、快くお引き受けいただいた校長先生に、心から感謝申し上げます。 ありがとうございました。 8/31 校長先生の「学校がよくわかる話・2」(2) ●依存することは自立につながる これまでは「自力で解決することに価値がある」とされてきました。 たしかに、自分で考えて、自分で調べて、自分で解決することは大切なことです。 でも、わからないときに誰かに頼ることは、いけないことでしょうか。 決してそうではないはずです。 他者に頼ることで、自分の知識が広がり、頼られた側も同じように知識が広がるはずです。 校長先生のお話から「依存する力を持つことは大切なこと。依存できる人は、必ず自立できる」ということを教えていただきました。 「依存できる」ということは「教えて」と言えることです。 このように、安心して「教えて」と言える、相手に依存できる関係を作ることが、「学び合う学び」の目指すことなのですね。 ●グループの形 校長先生が「グループには、リーダーは必要ないのです」とおっしゃったのには、ちょっと驚きました。 グループ活動をしていると、リーダーを作ったり、なるべく均等になるようにメンバーを入れ替えたりしますね。 しかし、「それは必要ない」とおっしゃるのです。 「どんな仲間と一緒になっても、互いに支え合い、学び合う、小さな社会を構築し、異質な価値観の中で『生きるためのかたち』を学ぶ場」と、校長先生はグループを定義されました。 人は、社会生活の中で、いろいろな人と関わりながら生きていかなければなりません。 好きな人、気の合う人とばかり付き合っていればよい、というものではないことは、保護者の皆さんは十分に承知していらっしゃることでしょう。 学校生活の中で、子どもたちは「社会に出るための練習」を積んでいるのですね。 8/31 校長先生の「学校がよくわかる話・2」(1) 前回、6月のPTA委員会後に初めて開催しましたが、とても好評でした。 今回のPTA委員会に多くの参加者があったのも、「校長先生のお話しを聞きたい!」という方が多かったおかげと、役員一同感謝しています。 今回の『校長先生の「学校がよくわかる話・2」』では、「小牧中学校の学び合う学び」という演題で、小牧中学校で力を入れている「学び合う学び」とはどういうことなのか、というお話しをしていただきました。 お話の中から、印象的だったことをいくつかご紹介したいと思います。 ●「学び合う学び」の効果 私たちが学生だった頃、学校の授業は「一斉授業」でした。 先生が「講義」をし、生徒はそれを「聞く」ことが仕事でした。 男子の列、女子の列と別れていて、ほとんど交わり合うことはありません。 今でも、そのような授業はいたるところで行われています。 しかし、ある調査結果によると、このような「一斉授業」の学習定着率は、なんと5%だそうです。 ところが、「学び合う学び」のように「互いに教え合う」場合には、学習定着率が90%と高くなります。 このことからも、小牧中の「学び合う学び」が、子どもたちにとって豊かな学びにつながることがかよくわかりました。 (この「学び合う学び」は、小牧中だけでなく、小牧市内の全小中学校で実施されています) また、この「学び合う学び」は、従来の、教師が一方的に講義をする授業とは異なるため、先生方の中にも戸惑いがあったということでした。 子どもたちが学び合うように、先生方も学び合い、すべての子どもが参加する授業を目指して勉強されているそうです。 このように、先生方の力量アップにも「学び合う学び」は効果があるのですね。 ●「わかる子が教えてあげること」が目的ではない 「学び合う学び」のように、グループになって相談したり、意見を出し合ったりする授業では、グループの中の「わかる子」が教えてあげるのは、よく見られることです。 わかる子が教えてあげることで、わからない子はわかるようになり、また教えた子も自分の理解が深まる、というよい循環が生まれます。 しかし、「本当に大切なことは、わからない子が、教えて、といえることなんです」という校長先生のお話しに、ハッとしました。 「教えて」と言える子は、「わかりたい」と思っています。 「わかりたい」という気持ちがなければ、いくら一生懸命に教えてあげても、その子には伝わりません。 どれだけ「意欲」が持てるかが大切なのですね。 「学び合う学び」が目指す「すべての子どもが参加する授業」は、この「意欲が持てる」ということにつながっているのだと思いました。 祝!小牧中HP「100万アクセス」 (【小牧中HP】100万アクセス御礼 9/1) 本当に、おめでとうございます。 これだけ多くの皆さんに訪問していただける学校HPは、他に類を見ないと思います。 「PTAの部屋」からも、代表してPTA会長より、心からのお祝いを申し上げます。 ☆☆☆☆☆ この度は100万アクセス達成おめでとうございます。 私も一人の保護者として、いつも学校の新鮮な情報、子供達の学校生活等を拝見させていただき、安心すると共に教職員の皆様の子供たちに対する愛情と情熱が伝わってきて感謝の気持ちが湧いてまいります。 このホームページ管理に関わるすべての方に、保護者を代表して御礼申し上げます。 また多くの方々にアクセスをしていただき、心から御礼申し上げます。 子供たちの様子だけでなく、私共PTAの活動も見ていただいていると言う事で、益々頑張らなくてはならないと励まされ、身も心も引き締まる思いです。 今後も引き続いて、精力的に学校を盛り上げて、皆様に関心をもって頂けるような情報を配信してもらえるように努力してまいります。 今後共、牧中ホームページをどうぞ宜しくお願い致します。 PTA会長 澤平敏秀 ☆☆☆☆☆ (おまけ) 小牧中HPのデザインが急に変わって「???」と思っておられる方もいらっしゃると思います。 校長先生が、お祝いの気持ちを込めて、新たなデザインに変更してくださいました。 ありがとうございました! 8/31 第4回 全委員会 台風の影響が心配されましたが、当日朝に学校より緊急メールにて「予定通り開催します」との連絡を流していただきました。 会場の変更もあり、ご参加いただいた委員の皆さまにはご迷惑をおかけしました。 今回も、たくさんの委員の皆さんにご参加いただき、ありがとうございました。 ●協議・連絡事項 1. 各委員会の活動報告 2. その他・学校からの報告 3. 連絡事項 澤平会長のごあいさつでは、1学期から取り組んでいる「愛マップ」について、以下のようなお話しがありました。 ********** 「愛マップ」(防災マップ)作りのために、関西大学の先生や学生さんたちと一緒に、子どもたちと実際にまち歩きをしたり、講義を受けています。 子どもにとって、大学の先生の講義を受けるのはとても貴重な機会になります。ぜひお子さんへ参加の呼びかけをお願いします。 ********** また、校長先生からは、1学期を振り返って、次のようなお話しがありました。 ********** 1学期から夏休みにかけて「いのちをテーマとした教育活動」を行ってきました。 先日、8/22の全校出校日では、鈴木中人さんに「いのちの授業」をしていただき、保護者も多数参加してもらいました。 また「愛マッププロジェクト」では、防災マップ作りを通して、子どもたちに「愛する人やものを守るためにどうすればよいか」ということを考えさせています。 1学期の学校の様子としては、まったくトラブルがないわけではありませんが、大きな問題はありませんでした。 校長が、度々出張や講演などで留守にできるのは、学校が落ち着いている証拠です。 ********** ●次回の予定(全委員会) 11/9(土)9:40〜10:10 多目的室 8/31 第3回 総務委員会 8/31(土)第3回総務委員会が開催されました。 ●協議・連絡事項 1. 9/7(土)父母と教師のつどいについて 2. 9/7(土)教育対話集会について 3. 9/21(土)体育大会について 4. 9/30(月)第2回学校公開日について 5. 10/16(水)給食試食会・食育講座について 6. 11/10(日)小牧市青少年健全育成市民大会について 7. 11/27(水)小牧市小中学校PTA研究発表会について ●その他 【体育大会について(昨年度の携帯アンケートから)】 昨年の体育大会後の携帯アンケートで、保護者からいくつか改善要望の意見が出ていました。 それらについて、その後の対応がどうなっているのか、お聞きしました。 ・開始予定時刻よりも早く始めていて、観戦に行ったのに間に合わなかった。 競技の開始時間は、進行具合により、多少の前後が発生してしまうが、なるべく予定どおりに行う。 午前の開始時間、午後の開始時間については、必ず予定時刻どおりに実施する。 ・60m走でスムーズな運営ができず、午前の終了時間が遅くなった。 60m走に出場する生徒数が多すぎる、ということが原因のひとつにある。 他の種目の出場選手数を増減して、60m走に集中しすぎないように配慮する。 ・もっと近くで観戦できるように、保護者の観覧席を検討してほしい。 生徒数が多いこともあり、生徒席周辺には十分なスペースがない。 また短時間で多くの競技を進めなければならないので、スムーズに生徒の移動ができるように、移動用スペースは確保したい。 そのため、現在のような、校舎側のみの観覧スペースにならざるを得ないことをご承知願いたい。 どのような競技が行われているか、進行状況はどうなのか、結果はどうなのか、といったことをお知らせするために、例年、放送委員の生徒がアナウンスをしている。 競技だけでなく、応援合戦なども、よりわかりやすくなるように、アナウンスの内容についても検討していきたい。 このように、アンケートで出た意見や要望に、真摯に対応していただけていることがわかり、とてもうれしかったですし、安心しました。 学校が、私たち保護者の意見を、きちんと受け止めてくれるということは、大きな信頼感につながっています。 今回のように、例えば「観覧席を新たに設けることはできないけど、アナウンスなどでわかりやすくする工夫をする」と、できる範囲で改善していただく姿勢を見せてくださることが、学校が「保護者の意見を大切にしたい」と考えていることを象徴しています。 すべてを改善することはできないでしょう。 しかし「検討したけど、やっぱり実現は難しかった」ということなら、保護者は納得しますし、このような学校の誠意ある対応に対して「できることは協力しよう」という気持ちになりますね。 今年の体育大会後にも、携帯アンケートが実施される予定です。 ぜひ、多くの保護者の方にご参加いただきたいと思っています。 「いいな、すばらしいなと思うこと」をお伝えするのはもちろん、「もっとこうしてほしい」という要望や「どうしてこうなっているのか」という疑問も、どんどんアンケートを利用して学校へ伝えていけるといいですね。 きっと、学校もそれを待っていると思います。
|
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||