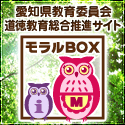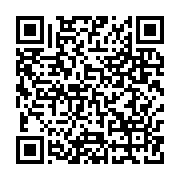|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:14 総数:156400 |
「第3回特別講座」で大人の学び(3)『最終回』 ☆「いのちをバトンタッチする会」HPはこちら ●いのちを大切にする 「身体のいのち」は限りがあります。 でも「心のいのち」は、無限のつながりがある、と鈴木さんはおっしゃいました。 死によって、「身体のいのち」は終わってしまっても、「心のいのち」は大切な人の心の中で、無限につながっていく、ということなのですね。 「いのちを大切にする」 これは、自分のいのちのことだけではありません。 支え合って生きている「仲間のいのち」も、同じように大切にしなければいけませんね。 ●家族の絆 「あなたのいのちは、あなただけのものではありません。あなたの両親、その両親、そのまた両親、と、誰一人欠けていても、あなたはこの世にいないのです。いのちのつながりは『家族の絆』なんですよ」と鈴木さんはおっしゃいました。 家族(家庭)は、ともに人生を営む場です。 そして、ともに危機を乗り越えて成長していきます。 家族は、深い愛情で支え合っているのですね。 それまで静かな口調でお話しされていた鈴木さんが、ここで大きな声で訴えました。 親より先に、死んではいけない。 あなたたちが死ねば、親は血の涙を流します。 どんなことがあっても、絶対に、親より先に死んではいけない! この鈴木さんの言葉は、すべての親の想いですね。 きっと、子どもたちにも「想い」が届いたと思います。 ●いのちの願い 鈴木さんは「いのちの願い」として、3つのことを教えて下さいました。 ・普通の生活の中で、小さな実践をする 家族や友達、周りの人々と「支え合う」こと。 「ありがとう」の気持ちを大切にすること。 しっかり「生き抜く」こと。 ・いのちを大切にしているか?問いかける いのちの言葉を心に刻む 「親より先に死んではいけない」 健康を保つことも大切 ・いのちはかけがえがない 一人のいのちは、多くの人に支えられ、愛されている、ということを忘れない ********** 今回の「いのちの授業」は、大人も子どもも、それぞれの立場で感じたことが違っていたかもしれませんね。 私たち保護者は、「親としての子どもへの想い」を持ちながらお話しを聞きましたが、しだいに、自分も子どもの立場で「両親への想い」も持つことができました。 ぜひ一度、お子さんから感想を聞いてみてくださいね。 照れくさがって、ちゃんと答えてくれないかもしれませんが、「たくさんの人に支えられ、愛されているいのちなんだ」とわかってくれたことと思います。 心に深く染み入るすばらしい授業をしてくださった鈴木中人さんに、心から感謝します。ありがとうございました。 ご協力いただいた先生方、PTA役員の皆さん、今回も本当にありがとうございました。 最後に、ご参加下さった大人の皆さま、生徒の皆さんへお礼を申し上げます。ありがとうございました! 「第3回特別講座」で大人の学び(2) ☆「いのちをバトンタッチする会」HPはこちら ●生き抜く 限りある「いのち」だからこそ、「一生懸命生きること」「生き抜くこと」が大切、と鈴木さんはおっしゃいました。 一生懸命生きれば、「いのちは輝く」のです。 鈴木さんの娘の景子ちゃんは、最後まで、一生懸命に生き抜きました。 だから、景子ちゃんのいのちは、今でも多くの人の心の中で輝いているのだと思います。 ●支え合う 人は、ひとりきりで生きているわけではありません。 鈴木さんは、景子ちゃんの闘病中に、多くの人に支えられていることに気付いた、とおっしゃいました。 それに気付くことができれば、自然と「ありがとう」という気持ちも生まれますね。 このように、人と人が支えあい、「ありがとう」が循環することが、他人も自分も幸せにすることなのですね。 ●困難と向き合う 自分の困難は、自分しか向き合えない、と鈴木さんはおっしゃいました。 景子ちゃんの病気が進行し、鈴木さんは心の底から「代われるものなら代わってやりたい」と何度も願ったそうです。 しかし、それは叶わぬことです。 誰しも、つらく苦しい困難を抱えることがあります。 そんな時は、思いっきり泣けばいい、たくさん涙を流せばいい、と教えていただきました。 「流した涙の分だけ幸せになれる」 それだけ一生懸命生きることで、いのちが輝くのですね。 ●寄り添う 困難は、当人しか向き合えませんが、周りの人々にもできることはあります。 それは「寄り添う」ことだと、鈴木さんはおっしゃいました。 人は「孤独感」に絶望するのです。 だから、「一人じゃない」という安心感が持てるように、寄り添ってあげてほしい。 ただそばにいて、静かに手を握ってあげたり、話を聞いてあげたりすること。 そうやって寄り添うことで、「一人じゃない安心感」を与えてあげられる、孤独感から救ってあげられる、と教えていただきました。 「第3回特別講座」で大人の学び(1) 娘さんの闘病のお話しでは、何度も胸が詰まり、多くの皆さんが目頭を押さえていらっしゃいました。 鈴木さんのお話しの中から学んだことを、いくつかご紹介します。 ☆「いのちをバトンタッチする会」HPはこちら ●小児がんの患者数から 現在、小児がんで闘病中の子どもは、全国で約20,000人。 小児がんは、子どもの死因の第2位だそうです。(第1位は交通事故) しかし、最近では医学の発達により、約7〜8割の患者は助かるそうです。 これだけ多くの子どもたちが、病気と闘っていて、行きたくても学校へ行けない現実があります。 誰でも一度は「学校へ行きたくないな」と思った経験はあるでしょう。 でも、そんな時には、この「行きたくても行けない子がいる」ということを思い出してほしいのです。 行きたくても行けない子の分も、あなたはがんばらなければいけない、ということではありません。 子どもたちには「学校に行けることは幸せなことだ」ということを、忘れないでほしいと思います。 「自分は幸せだな」と素直に思える人であってほしいと思います。 ●いのちは不思議 日本の年間自殺者数をご存じですか? 昨年は10数年ぶりに若干減少しましたが、約30,000人のいのちが、毎年自殺により失われています。 自殺未遂の人は、その10倍の人数にのぼると言われています。 約300,000人。小牧市の人口の約2倍です。 小児がんの「いのち」は、「もっと生きたい」と願ういのち 自殺する「いのち」は、「もっと生きられるのに」あきらめてしまういのち 人は必ず死を迎えます。死と向き合わない「いのち」はありません。 限りある「いのち」だからこそ、「本当に大切なことに気付くこと」が「自分を幸せにすること」だよ、と鈴木さんに教えていただきました。 新しいこと始まりました!「第3回親子で学ぶ小牧中特別講座」 今回は、「ぜひ子どもたちに聞かせたい」という校長先生の想いから、全校出校日の開催となり、会場も小牧市民会館で行うことができました。 子どもたちは、暑い中、学校から歩いて市民会館へ移動したので大変だったでしょうが、しっかりした態度で講演を聞いている姿は、とても立派でした。 今回の特別講座は、区長会のご厚意で、各町内の回覧板で案内チラシを回覧していただいたこともあり、保護者だけでなく、地域の方がたくさん参加して下さいました。 また、他市から参加して下さった方もありました。 講師の鈴木中人さんは、小児がんで娘さんを亡くされています。大変、つらく苦しい経験をされました。 そして、現在は、小児がんの子どもを救うために、小児がんの子を持つご家族を支えるために、さまざまな活動をされています。 ご自身の経験を、静かに語る鈴木さんのお話しをお聞きしながら、参加した大人・子ども、それぞれが「いのち」について、静かに想いを巡らせました。 とてもすばらしい時間になりました。 貴重な時間を与えて下さった鈴木中人さん、ありがとうございました。 また、先生方による学校の支援に深く感謝しています。 そして、足を運んで下さった皆さま、本当にありがとうございました。 【合わせてご覧ください】 鈴木中人さんが代表をされている「いのちをバトンタッチする会」HPはこちら 「第3回親子で学ぶ小牧中特別講座」へのお誘い 楽しい思い出は、たくさんできたでしょうか? さて、8/21(水)は「全校出校日」です。 この日に提出しなければいけない課題も多いと思います。 忘れていて、当日に慌てなくてもよいように、保護者の皆さんからお子さんに、一声かけてあげられるといいですね。 この日は、「第3回親子で学ぶ小牧中特別講座」が開催されます。 今回の特別講座は「特別バージョン」です。 子どもたちと一緒に、市民会館で、鈴木中人さんの「いのちの講演」をお聞きします。 親子で同じお話しを聞くことができる貴重な機会ですので、ぜひ多くの保護者の皆さんに参加していただいて、ご家庭で、親と子のそれぞれの「いのち」についての想いを話し合うきっかけにしてもらえるといいなと思います。 この特別講座は、小牧中の保護者だけでなく、どなたでもご参加いただけます。 区長会のご厚意で、先日、案内チラシを、各町内で回覧していただきました。 地域の皆さまも、ぜひ足をお運びください。 ● 日時 8/21(水)10:20〜11:40 (受付開始 10:00) ● 会場 小牧市民会館 大ホール (1階席は生徒が使用しますので、保護者や地域の方々は2階席をご利用ください) なお、案内チラシは、右欄の「配布文書」よりご覧いただけます。 8/21(水)10:20〜11:40 (受付開始 10:00)</font> ● 会場 小牧市民会館 大ホール (1階席は生徒が使用しますので、保護者や地域の方々は2階席をご利用ください) なお、案内チラシは、右欄の「配布文書」よりご覧いただけます。 <swa:ContentLink type="doc" item="12139">(第3回特別講座チラシ)</swa:ContentLink> 【関連記事】 <a href="http://swa.komaki-aic.ed.jp/weblog/index.php?id=komaki_j_pta&type=1&column_id=104786&category_id=1507" target="_blank">【PTAの部屋】「第3回親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! 7/19 長崎「原爆の日」に想う 先日の学校HPで、校長先生が中学生時代の恩師の言葉を引用された記事を掲載して下さいました。 中学生の皆さんに、「平和宣言を読んで、自分の置かれている環境について考えてほしい」というメッセージでした。 (「広島『原爆の日』に想う」に思う 8/7) 昨日の、長崎市長の平和宣言では、とくに若い世代の人々へのメッセージがとても印象的でした。 一部を引用します。 -----*--(引用開始)--*----- 若い世代の皆さん、被爆者の声を聞いたことがありますか。 「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ウォー、ノーモア・ヒバクシャ」と叫ぶ声を。 あなた方は被爆者の声を直接聞くことができる最後の世代です。 68年前、原子雲の下で何があったのか。 なぜ被爆者は未来のために身を削りながら核兵器廃絶を訴え続けるのか。 被爆者の声に耳を傾けてみてください。 そして、あなたが住む世界、あなたの子どもたちが生きる未来に核兵器が存在していいのか。 考えてみてください。 互いに話し合ってみてください。 あなたたちこそが未来なのです。 -----*--(引用ここまで)--*----- 「平和」がどれだけ幸せなことなのか、大人も子供も、改めて考えたいですね。 そして「いのち」についても、ぜひ想いを寄せてほしいと思います。 戦争、原爆という理不尽な力によって、無残に散ってしまった数え切れない「いのち」があります。 「生きたい!」と願っても叶えられなかった、多くの「いのち」 今を生きる子どもたちには、そういう「いのち」がたくさんあったことを忘れず、自分の「いのち」も他人の「いのち」も同様にかけがえなのない大切なものだ、ということを、心に刻んでほしいですね。 ※写真は長崎市HPから引用しています。 ちなみに、写真の像は有名な「平和祈念像」ですが、その意味を先日の佐藤先生の講演会で教えていただきましたので、合わせてご紹介します。 神の愛と仏の慈悲を象徴し、垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命 を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている。被爆10周年にあたる1955年8月8日に完成。(Wikipediaより引用) 【関連記事】 ●長崎市HP (平成25年度長崎平和宣言 8/9) 佐藤先生講演会で「大人の学び」(2) 【関連記事】 ●小牧中HP (夏季教職員研修(2) 8/7) ●佐藤正寿先生ブログ「地域のよさ・日本のよさを伝える授業」 (新分野で講師 8/7) ● ライフステージを見据える 佐藤先生は、教師としての時間を3つのステージに分けて、それぞれのステージで何をすべきか、ということをお話しして下さいました。 ・第1ステージ(20代〜30代半ば)教師としての基礎を学ぶ世代 ・第2ステージ(30代半ば〜40代後半)学校の柱として活躍する世代 ・第3ステージ(40代後半〜退職)学校のリーダー、後輩を育てる世代 保護者の皆さんも、同様にそれぞれの世代に分かれますね。 そして、それぞれの世代の役割を、会社や地域など、社会の中で担っていらっしゃることと思います。 佐藤先生がおっしゃっていたのは、常に先のステージのことを見据えて、次のステージのために「今できること・今すべきこと」を具体的に考えていくとよい、ということでした。 次のステージの目標を定めることで、そこへ到達するための一年一年の行動を具体化することが大切だよ、と教えていただきました。 日々の生活の中で、どうしても目先のことにとらわれがちですが、先のステージを見据えた「未来の自分」について考えてみるといいですね。 ● 人間関係力 人が社会生活を営む上で欠かせないのが「人間関係を円滑に築く力」ですね。 教師であれば、「子どもとの人間関係」「職場での人間関係」「保護者との人間関係」ということが主に挙げられますが、これらの人間関係がうまくいかないと、いくら授業が上手だったとしても、学校の中で孤立してしまうことになりかねません。 「保護者との人間関係」について、最近は「モンスター・ピアレント」という言葉が一般化しているように、対応が難しいケースが多いそうです。 しかし、佐藤先生はおっしゃいました。 「教師と保護者は、子どもをよくしたい。立派に育てたい。という思いは共通のものを持っている。だから、保護者は敵ではなく、味方なんですよ」 まったく、そのとおりだと思います。 立場は違っても、願っていることは同じなのですから、きちんと思いを伝え合えば、必ず分かりあえるはずだと思うのです。 先生も保護者も、それぞれがお互いの立場を尊重し合って、「子どもたちのために」という同じ気持ちで、信頼関係が築けるといいですね。 ● 子どもの「ドキドキ」を体験する 今回の講演会は、ずっとお話ばかりだったわけではありません。 「地名あてクイズ」などの小学校の社会科の問題を使って、模擬授業のようなこともありました。 誰もが習ったはずの、小学校の社会の問題でしたが、意外とうろ覚えで「あれ?どうだったっけ?」ということが多かったのです。 先生の指示で、隣近所の席の人たちと相談するのですが、予想外の答えが飛び出したりして、けっこう面白く、楽しい時間でした。 みんなで相談している間、佐藤先生は、ニコニコしながら歩きまわって、みんなの様子を見ています。 「話し合いを止めて」の指示のあとは、「次、当てられたらどうしよう。自信ないからイヤだなぁ」と、ドキドキし通しでした。 授業中、子どもたちも、きっと同じ思いをしているのでしょうね。 「当てられたらどうしよう・・・ドキドキ」 久しぶりに生徒に戻って、子どもたちのドキドキを体験しました。 がんばってるんですね!子どもたち。えらいぞ(笑) 今回、たくさんの皆さんのお力添えで講演会に参加することができ、本当に感謝しています。 佐藤先生、とても多くの学びを、ありがとうございました。  佐藤先生講演会で「大人の学び」(1) 教員向けの講演でしたが、教員でなくても、とても学びの多い講演でした。 学校HPでも記事が掲載されていますが、小牧中からも多くの先生方が参加されており、先生が自ら学ぶ姿勢を示して下さっていることに、保護者としてとても心強く感じました。 講演をお聞きして感じたことのいくつかを、ご紹介したいと思います。 【関連記事】 ●小牧中HP (夏季教職員研修(2) 8/7) ●佐藤正寿先生ブログ「地域のよさ・日本のよさを伝える授業」 (新分野で講師 8/7) ● 演題・講師 「価値ある出会いと学びが教師を変える〜教師力を高めるために〜」 岩手県奥州市立常盤小学校 副校長 佐藤正寿先生 ● 講演会では知識を学ぶのではなく、考え方を知ること。 佐藤先生は、現在、岩手県の小学校の副校長(教頭)先生をされています。 皆さんもご存じのとおり、教頭先生といえば「学校で一番忙しい先生」であると言っても過言ではありません。 そんなお忙しい身でありながら、各地で講演会をされているのは、ご自身が学ぶためでもある、とおっしゃいました。 佐藤先生は、ご自分が講演をされるばかりでなく、よく講演会や研修会に聴衆として参加されるそうですが、その中で学んだことに「講演会では知識を学ぶのではない。考え方を知ることだ」という言葉があるそうです。 「知識」は単なる情報として、頭の中を通り過ぎてしまうこともありますが、「考え方」となると心に残りやすくなります。 また、いろいろな考え方を知ることで、物事をいろいろな角度で見ることができるようになる、ということだと思います。 「人の意見や考え方を聞く」ということは、「自分の考え方をより豊かにしてくれることなんだ」ということを、改めて感じました。 子どもたちは、授業の中でよく4人組になって話し合っています。 その姿と、佐藤先生のお話しが重なって「なるほど。4人組には、そういう狙いもあるんだな」と納得しました。 ● 人間性を磨く 「教師として学ぶだけではなく、私は人間として自分自身を磨くことも大切と考えている」と、佐藤先生はおっしゃいました。 自分に合った方法で学び続けることが、自分の人間性を磨くことにつながり、それは必ず子どもにもよい影響を与えることができる、ということです。 これは、教師に限らず、私たち保護者にも言えることですね。 身近な大人である親が、生き生きと学び続けている姿を子どもたちに見せることができれば、子どもはきっと「大人になるのも悪くないな」と感じてくれるのではないでしょうか。 自分自身のためにも、子どもたちのためにも、「学び続ける大人」でありたいものですね。  広島「原爆の日」に想う 皆さんもご存じのとおり、68年前の今日、広島に原子爆弾が投下され、一瞬にして多くの命を奪いました。 今日の平和記念式典では、この1年間に死亡が確認された方や、新たに亡くなった方5,859名の名前が書き加えられ、総勢28万6,818名になった原爆死没者名簿が、原爆慰霊碑に納められたそうです。 私たち保護者全員が、広島の原爆投下については、学校で学んできました。 もちろん、子どもたちも学んでいます。 これからも、世界で唯一の被爆国である日本の国民として、学び続けていかなければならないことですね。 「起こった事実」を教科書で学ぶことはできます。 しかし、実際に体験した人の話を聞くことや、被爆地を訪れて本物の資料を見ることで、実感につなげることができますね。 実感につながったほうが、より理解が深まると思います。 でも、戦後68年が経ち、当時を知る人たちは、年々減ってきています。 子どもたちの祖父母の世代(私たちの両親の世代)でも、戦争を経験していない人が増えています。 戦争の悲惨さを風化させず、子どもたちに伝えていくために、「語り継ぐこと」の重要性がとても高まっていると感じます。 子どもたちには、年に一度、この時期だけでも、戦争で起こった悲劇について、しっかりと目で見て、耳を傾けてほしいと願っています。 今日の平和記念式典には、福島の原発事故の影響で全町民が避難を余儀なくされている浪江町の町長さんも参列されていた、とニュースにありました。 「爆弾」「発電」と形は違いますが、今日のニュースが「原子力」についてご家族で考えるきっかけになるといいですね。 ※写真は、中日新聞HPから引用しています。今日の原爆ドームの様子です。 松江からのお客様に「PTAの部屋」のご紹介  おもに、本校の「ICT活用」についての視察で、学校支援システムが実際にどのように使われているか、業務軽減にどのような効果があるのか、といったお話しが中心でした。 新装されたばかりの「コンピューター室」なども見学されました。 校長先生のお気遣いにより、今回の視察の中で、「PTAの部屋」について簡単にご紹介させていただく機会をいただきました。 学校と保護者をつなぐツールとして「PTAの部屋」を運営していること、今後も、PTA活動の報告・紹介をベースに、さらに保護者の想いの発信を通じて、学校HPとの連携を続けていきたいことなどをお話しさせていただきました。 貴重な機会をいただき、ありがとうございました。 (副会長・斎藤) 小牧中のお宝(5) 元WBC世界チャンピオンの薬師寺保栄氏を、ご存じですか? 保護者の皆さんは、よくご存じだと思います。 彼が小牧中学校出身だということも、同年代の方には有名な話です。 しかし、残念ながら、子どもたちのほとんどが「誰、それ?」という状況のようです。 薬師寺保栄氏は、第23代WBC世界バンダム級王座で、4度の王座防衛を果たしています。 辰吉丈一郎氏とのWBC世界バンタム級王座統一戦は、史上初の日本人同士による王座統一戦として、日本中から大きな注目を浴びました。 (Wikipediaより引用) その薬師寺氏が、現役引退後に、母校である小牧中を訪問し、講演会が開催されたそうです。 その時に寄贈されたのが、このボクシンググローブだそうです。 実はこのお宝、現在は展示はされておらず、多目的室のロッカーの中で眠っていました。 今回のお宝情報も、前校長の清水先生に教えていただきました。 先生方の中でも、この存在をご存じない方が多くて、少し残念ですが、清水先生に教えていただいたおかげで、こうして発掘できて、写真を皆さんにお見せすることができたので、本当によかったです。 清水先生、ありがとうございました。  「通知表」のおはなし 保護者の皆さんは、毎日の昼食の準備が増えて、給食のありがたさを実感する毎日ですね。 夏休みに入る前の一大イベント、「通知表」 もちろんご覧になっていますよね? 1年生の保護者の方で、初めて小牧中の通知表を手にされた方は、ちょっと驚かれたと思います。 小牧中の通知表は、ファイル形式になっています。 そして、中には、評定だけでなく、「通知表ファイルの見方」「健康診断の結果」「活動の記録」などのプリントも入っています。 1学期には数ページしかない「通知表ファイル」ですが、学期ごとにプリントが増えていきますので、学年末にはけっこうなボリュームになります。 終業式の日に、学校HPに、通知表に関する記事が掲載されました。 その中で、校長先生が『「通知表ファイルの見方」を改訂しました』と書かれていました。 (通知表を渡す風景 7/19) この「通知表ファイルの見方」、『実はあまりよく読んだことないのよね・・・』という保護者の方がけっこういらっしゃるのではないでしょうか。 せっかくの機会ですから、ぜひ一度じっくり読んでみてはいかがでしょうか。 「はじめに」に書かれている、『通知表の形式や内容は学校で独自に決めてよい』『通知表を発行するかしないかまで学校で決めることになっている』という部分は、驚きですね。 「通知表を発行しない」という学校はあまりないでしょうが、その形式はいろいろと学校ごとに違いそうですね。 小牧中の通知表が、小学校のときのものと大きく違っているのも、そのような自由度が認められているから、ということなのですね。 さて、通知表で一番気になるのは、もちろん「評定」ですね。 ここは数字でバーンと出ますので、とてもわかりやすく、一喜一憂のタネになります。 その評定の評価の仕方についても、「通知表ファイルの見方」では説明されています。 「観点別評価」でどれだけ目標に対して実現できているか、という判断をし、それをもとに「総合的に」子どもの状況を表したものが「評定」となるそうです。 どのように評定が決められるのか、また、評定の数字の意味するところはわかります。 でも、保護者が一番知りたい、例えば「具体的には、どうやったら”5”がつくのか?」ということは、やはりよくわかりませんね。 そこがわかれば、子どもにがんばらせるのに・・・と思っておられる保護者もいらっしゃるでしょうが、教科によっても、学年によっても、評価の方法は異なっているため、そこは先生方にお任せするしかないようです。 定期テストの結果は、もちろん評定に影響します。 しかし、それだけではなく、課題の提出状況や、授業中の取り組みの姿勢なども考慮されていて、それらを総合的に判断して、評定が決定します。 ですから、日常的な取り組みが、とても大切なのですね。 「通知表」は、今学期の子どものがんばり具合を確認するためのもので、「叱るための材料」ではありませんよね。 子どもたちは、担任の先生から通知表を渡してもらうときに、激励の言葉をもらっています。 私たち保護者は、思うような結果でなかったら、ついつい小言を言ってしまいますが、できれば、がんばったことはしっかりほめてあげたいですね。 その後で、次はどこをがんばったらいいか、と子どもと一緒に考えていけるといいですね。 「第2回特別講座」で大人の学び(2) ●落語家と教師の共通点 「特別講座」終了後、校長先生をはじめ、学校の先生方と、PTA役員で、桂雀太さんを囲んで懇親会を開催しました。 いろいろと楽しいお話しをお聞きしましたが、その中でとくに興味を持ったのが「落語家と教師の共通点」のことでした。 雀太さんは「落語はリズムが大切」とおっしゃいましたが、それを聞いて校長先生も「授業もリズムが大事だよ」と教えて下さいました。 落語家さんは「リズム」を意識して、よりお客様に伝わる語りを心がけるそうです。 一方、授業でも、先生方は授業の流れのリズムを意識することが大切なのだそうです。 一見関係のないような「落語」と「授業」に、意外な共通点があることがわかって、とてもおもしろかったです。 ●落語は文化 最近は、テレビなどで落語を見ることが、ほとんどありません。 「難しそう」という印象を持たれている方も多いと思います。 実際に「生」で見てみると、決して難しいものではないことがわかります。 わざわざ足を運ばなくても、インターネット上にはいくつも動画がアップされていますので、気軽にご覧になってみてはいかがでしょうか。 扇子や手ぬぐい以外の小道具は一切使わず、映像などの演出なしで、「語り」だけで演じる「芸」である落語は日本の大切な「文化」だと思います。 子どもたちにも、この文化を楽しんでもらえるといいなと思っています。 桂雀太さん、大阪からわざわざ来て下さり、本当にありがとうございました。 そして、今回も企画して下さった校長先生に感謝しています。 準備から後片付けまで協力して下さった先生方、PTA役員の皆さん、ありがとうございました。 参加して下さった大人たち、子どもたち、皆さんありがとうございました!  「第2回特別講座」で大人の学び(1) とても楽しい時間になりました。 笑って、笑って、の大爆笑でしたが、ちゃんと学びもありましたよ。 校長先生のインタビューと合わせて、ご覧ください。 (「第2回親子で学ぶ小牧中特別講座」(桂雀太さんへのインタビュー) 7/24) ●演目のあらすじ 「青菜」 ある植木屋が、夏の暑い日に、大きな御屋敷で庭の手入れをしています。 今日の作業が終了したので、家の主に声をかけて帰ろうとしたら、主人に「酒の相手をしてくれないか?」と誘われます。 植木屋は、主人に勧められるまま、よく冷えたおいしいお酒(柳陰)や鯉のあらいをいただきました。 最後に、主人が「青菜でも出しなさい」と奥さんに言いつけましたが、残念ながら青菜は食べてしまってない、と伝える奥さんと主人との会話が粋で、植木屋はいたく感動します。 自分の家に帰って、事の顛末を女房に話し、自分たちも真似してやってみようとしますが、そこはただの庶民の二人。一生懸命やってみますが、どこかちぐはぐで、その様子がとってもおかしい、というお話し。 「代書屋」 昔は、文字が読めない、書けない、という人がたくさんいて、代わりに「字を書いてくれる」という代書屋さんという職業があったそうです。 ある男が「履歴書」を書いてもらうために訪れた代書屋さんでの、男と代書屋の親父さんのやり取りのお話し。 この男(マツモトトメゴロウ・通称トメさん)、とにかくとんちんかんで、代書屋の親父の質問に、どれひとつまともに答えられません。 代書屋の親父が、トメさんにわかるように、いちいち噛んで含めるように説明する様子と、それに的外れな答えを返すトメさんの様子が、おかしくておかしくて誰もが大笑いするお話し。 ●「見える」情景 落語家さんのすごいところは、身振り手振りで話をしているだけなのに、聞き手には「情景」が思い浮かぶことです。 今回も、初めて落語を聞いた、という人は、皆さんが「すごい!見たこともないものなのに、その光景が見えた!」という感想を持ったようです。 雀太さんが、校長先生のインタビューの中でおっしゃっているように、「登場人物がそこにいるだけで笑える落語」というのは、その情景が想像できなければ難しいことです。 落語家さんは、お客様に「情景が見える」ような、さまざまな工夫をしておられるのですね。 まさに「芸」だなぁ、と感心しました。 ●落語家の流儀 「眼鏡」 昨年の「第1回親子で学ぶ夜の小牧中学校」に来て下さった桂紅雀さんもそうでしたが、今回の桂雀太さんも、普段は眼鏡をかけていらっしゃいます。(ちなみに、我らが愛狂亭三楽さんも、眼鏡かけてます) しかし、高座に上がるときには、眼鏡ははずします。 落語をするときは、余計な装飾物はつけないのが流儀だそうです。 ひどい近視の方だと、お客さんの顔は全然見えないでしょうね。 かえってそのほうが、緊張を和らげるにはいいのかもしれませんね。 「着物」 高座に上がる落語家さんは、いつも羽織を着ていらっしゃいます。 「まくら」と言われる、始めの世間話や小噺が終わり、本題の演目に入ったころに羽織を脱がれることが多いようですが、とくに決まりはないようです。 また、途中で休憩が入る場合は、着物を着替えられます。 コンサートで歌手が衣装替えするのと同じですね。 小牧中のお宝(4)
今回の「小牧中のお宝」は、有名な画家さんの、直筆スケッチです。
「有名な画家」というのは、山下清画伯です。 「裸の大将」というテレビドラマシリーズで、皆さんよくご存じだと思います。 あの「おにぎり大好き」な山下清画伯が、なんと小牧中を訪問したことがあり、さらに直筆のスケッチを残していたとは! 山下さんが、小牧中を訪問したのは、昭和43年2月20日。 特殊学級(現在の特別支援学級)を訪問し、生徒と交歓。スケッチを遺した。 ということですが、どうして小牧中を訪問したのかなどの詳細は不明です。 このときに書かれたスケッチは、今も「10・11組」の教室の壁に掲示してあります。 45年前に書かれたものですが、きれいに保存されていたようで、今でも線や色がはっきりしています。 卒業生でも、このスケッチの存在を知らない人が多いようですが、これは小牧中のすばらしいお宝ですね! ぜひ、お子さんにも教えてあげて下さいね。    【コーラス】7/21 活動報告 今回は、飛び入りの方もいて、なんと9名(!)で練習することができました。 人数が増えたおかげで、初めてパート練習もでき、とても活気のある練習会となりました。 ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 コーラスクラブでは、常時メンバーを募集しています。 見学だけでも大歓迎!ぜひご参加ください。 ● 次回以降の練習日 9/15(日)、9/22(日)それぞれ10〜12時 練習場所は未定です。決定しだい、「PTAの部屋」にお知らせをアップします。  新しいこと始まりました!「第2回親子で学ぶ小牧中特別講座」 夏休みに入ったばかり、しかも子どもたちは市内大会の真っ最中、という中でしたが、大人の方を中心に、子どもたちも参加してくれました。 今回は、桂雀太さんから学ぶ「落語の世界」です。 「初めて”生”で落語を聴く」という方が、全体の3分の1程度で、もちろん子どもたちも初体験となりました。 桂雀太さんの落語は「青菜」と「代書屋」の2本。 途中、玉置校長先生によるインタビューも交え、大人も子どもも存分に笑わせていただき、とても楽しくてためになる時間となりました。 暑い中でしたが、大阪から駆け付けて下さった桂雀太さん、ステキな時間をありがとうございました。 また、ご参加いただきました皆さま、子どもたち、本当にありがとうございました。 「第3回 親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! ご案内のチラシを作成し、お子さんを通じて配布させていただきました。 夏休みに入るため、ちょっぴり早めのご案内になりました。 しかし、夏休み前の、ただでさえプリント類の多い時期なので、保護者の皆さんのお手元に届くかどうか・・・ ということで、今回も右欄の「配布文書」でご覧いただけるようにしました。 ぜひご活用ください。 8/21(水)第3回親子で学ぶ小牧中特別講座が開催されます。</b> ご案内のチラシを作成し、お子さんを通じて配布させていただきました。 夏休みに入るため、ちょっぴり早めのご案内になりました。 しかし、夏休み前の、ただでさえプリント類の多い時期なので、保護者の皆さんのお手元に届くかどうか・・・ ということで、今回も右欄の「配布文書」でご覧いただけるようにしました。 ぜひご活用ください。 <swa:ContentLink type="doc" item="12139">(第3回特別講座チラシ)</swa:ContentLink> 「第3回」は、いつもとはちょっと趣向を変えて開催します。 開催日の「8/21」は、小牧中の全校出校日です。 この日に開催することには、校長先生の深い想いがあるのです。 今年、小牧中では「命を実感するプロジェクト」を始動させ、いろいろな取り組みが始まりました。 今回の「第3回」は、「命を実感するプロジェクト」の一環でもあり、「鈴木さんのお話しを全校生徒に聴かせたい!そして、保護者にもぜひ一緒に聴いてほしい!」という校長先生の想いが「形」になったものです。 親子で一緒にお話しを聴くことは、親は親の立場で、子どもは子どもの立場で、それぞれが「いのち」を考える時間になります。 さらにご家庭でも、親と子が「いのち」について考えたことを話し合って、それぞれの想いを共有できるといいですね。 ● 日時 8/21(水)10:20〜11:40 (受付開始 10:00) ● 会場 小牧市民会館 大ホール (1階席は生徒が使用しますので、保護者や地域の方々は2階席をご利用ください) ● その他 事前の申し込みは不要です。直接会場へお越しください。 小牧中の生徒や保護者だけでなく、どなたでもご参加いただけます。 お誘い合わせの上、ぜひご参加ください! 【関連記事】 小牧中HP<a href="http://swa.komaki-aic.ed.jp/weblog/index.php?id=komaki_j&type=1&column_id=96454&category_id=1196" target="_blank">「いのちをバトンタッチする会代表・鈴木中人さん来校 4/10」 【教養】7/17 教養講座   定員に余裕があったため、学校から先生方にもご参加いただき、講師の福富先生のご指導のもと、作品づくりに挑戦しました。 先生が用意してくださった、たくさんの種類のパターンペーパーや、型の抜きの道具などに目移りしながらも、「写真に合う柄は?」「どんな飾りにしようか?」とワクワクしながら、あっという間に完成。 最初に「写真は撮ったままで終わらずに、素敵に加工して飾ることで、家族の宝物になるんですよ」と先生のおっしゃった通り、世界に一つだけの宝物になりました。 講師の福富先生、ご参加の皆さま、ありがとうございました。 「第2回親子で学ぶ小牧中特別講座」へのお誘い 今回は、昨年度の「夜の小牧中」でもとても好評だった「落語」です。 大人も子どもも、みんなで楽しみましょう! 小牧中の生徒や保護者でなくても、どなたでもご参加いただけます。 お誘いあわせの上、ぜひ小牧中へお越しください。 玉置校長先生の「落語評論」が、小牧中HPに掲載されています。 ご覧になれば、見たくなり、聴きたくなること請け合いです! ぜひご一読ください。 (「桂雀太さんから学ぶ落語の世界」のお勧め 6/28) ● 日時 7/20(土) 16:00〜17:30 ● 会場 小牧中 多目的ホール(2階の玄関よりお入り下さい) |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||