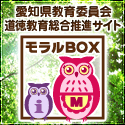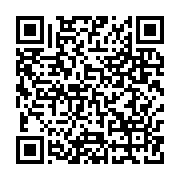|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:14 総数:156399 |
「子どもとの会話」に想う 結果はともかく、「終わった」ということで、やれやれと胸をなで下ろされている保護者も多いのではないでしょうか。 さて、なんとか無事にテストを終えた子どもたちに、どんな言葉をかけたらいいのだろうか・・・と考えさせられたのが、昨日の学校HPの「子どもとの会話」の記事でした。 (子どもとの会話 6/27) この野口さんが言われる「その子どもが抱いた気持ちの原因になる部分の、その子どもの責任に関わることを意識させていくこと」となると、どのような会話をすればよいのでしょうか。みなさんで意見交換をしたい気持ちになりました。そして、我が子育てを振り返り、ため息をついたところです。 校長先生は、記事の中でこのようにおっしゃっておられますが、「先生自身も、親としては、私たちと同じように自信がなかったんだな」という、ちょっとホッとする思いがして、とても共感できますよね。 それと同時に、「先生もわからないんじゃ、私たちにわかるわけないじゃん!」と困ってしまいました。 保護者の皆さんそれぞれに、いろいろな意見をお持ちでしょうね。 どれが「正解」ということではなくて、皆さんが我が子のことを想って、一生懸命考えた言葉がきっと一番よいのではないでしょうか。 例えば、思い通りの結果でなかったのなら、とにかく頭ごなしに「何やってるの!ダメでしょう!」というのは避けて、「どうしてできなかったのか?」の原因を、子どもと一緒に考えてみるのがいいかもしれませんね。 きっと、子どもなりに「原因」はわかっています。 それを子どもの口から言わせることで、きちんと自覚してくれるはずです(と信じたいですね) 「原因」がわかったところで、すぐに改善できないのが子どもです(大人もそうですよね) 長い目で見守っていきたいですね。 と、悠長なことを言っていられるのも今日だけかもしれません。 来週、次々と返却されるテストを見て、頭に血が上らないことを心から願っています(笑)
|
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||