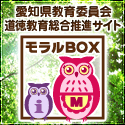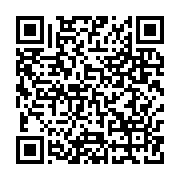|
最新更新日:2024/05/12 |
|
本日: 昨日:14 総数:156326 |
FM AICHI オンエアのご紹介 ぜひお聴きください! ※キャンペーン紹介ページはこちら 【FM AICHI(80.7MHz)】 10/28(月)〜11/1(金) 18:55〜19:00 【コーラス】10/27 活動報告   いよいよ、文化祭の発表に向けて、最後の練習日です。 まずは「衣装合わせ」 本番用の衣装を身にまとったコーラス部員の皆さんは、いつも以上に輝いて見えますね! 練習も、本番に向けて、いつも以上に真剣に取り組むことができました。 初めての舞台で緊張しますが、メンバーの心を一つにして、皆さんに素敵な歌声をお届けしますので、ぜひ聴いて下さい。 【文化祭の発表】 11/1(金) 11:45〜 「PTA合唱」 その後、先生方の「職員合唱」もあります 【市P連】10/25 母親委員会   土屋さんから報告の写真とコメントをいただきましたので、ご紹介します。 ********** 10/25(金)、市P連の母親委員会に参加してきました。 犬山市の老舗和菓子店「若松屋阡壱」の後藤豊正氏を講師にお迎えし、各校の母代さんと和菓子作りに挑戦しました。 和菓子は、見た目をキレイに仕上げることが大切で、形を整えるのが難しく、皆さん悪戦苦闘していました。 白のお菓子は「白菊」、ピンクのお菓子は「へら菊」といいます。 和菓子作りの研修会のあとに、茶話会がありました。 同じ母代同士、学校行事のことや近況などを、楽しく情報交換できました。 自分の学校のことだけでなく、他校の様子を聞くことができる機会は、とても貴重です。 他校の活動の様子は、とても参考になり、楽しい時間を過ごすことができました。 ********** 【市P連】10/19 県教育研究会 土屋さんからレポートをいただきましたので、ご紹介します。 ********** 10/19(土)ウインクあいちで開催された、「第63次教育研究会愛知県集会」に参加してきました。 講師は、奈良文化女子短期大学教授の善野八千子さん。 「力と夢を育てる地域ぐるみの学校づくり」という演題で、お話しをしていただきました。 講演会途中で、会場内の参加者が二人一組になり、お互いの子ども(生徒)自慢を話す、というおもしろいプログラムになっていました。 講演の中で、とくに心に残ったことは ・性格や生活は、けじめの時期に変えることができる ・命はリセットできない ということでした。 先生は「命の重さより、命のはかなさ」ということについて、よく大学生にもお話しをされるそうです。 「命のはかなさ」を知ってもらうために、参加されてた教師の皆さんに ・赤ちゃんが教室にやってくる ・マタニティの方が生で語る ということを実現してみるとよい、とアドバイスをされているそうです。 善野八千子先生は、とても明るい方で、こんなこともおっしゃいました。 「目指す学校づくりは、『人づくり』『町づくり』『若作り』!」 とても楽しく、勉強になるお話しを伺うことができました。 ********** 【コーラス】10/15 活動報告 いつも練習している音楽室とは違い、体育館は広い空間で、天井も高いので、お腹からしっかり声を出す練習に専念しました。 本番まで、練習はあと一回です。 当日は、すばらしいハーモニーをお聴かせできるように、がんばります! 【次回の練習日】 10/27(日)10:00〜12:00 ●持ち物 本番で着る衣装(上下とも)、黒のパンプス 【コーラス】10/13 活動報告   今日は、大学でも行われているという「発声法」を教えていただきました。 この「発声法」をやってみると、驚くように声が出るようになり、やる前とやった後では、声の大きさがずいぶん変わったことを実感して、とても驚きました。 一番身体の力が抜ける方法だそうです。 【生指】10/12 ジュニア奉仕団支援   10月だというのに、日差しの当たるところは、ジリジリとしてくるほどの好天気の中、たくさんの生徒の皆さんが参加してくれました。 前回の盲導犬募金の日に比べて、アピタへの人の出入りが少なめだったのですが、生徒たちは、大きな声で募金の呼びかけをしていました。 このように、中学生がボランティア活動をしている姿を、ひとりでも多くの地域の皆さんに見てもらえることが、意義のある活動だと思います。 参加してくれた生徒の皆さん、世話人の皆さん、そして当番の生徒指導委員の皆さん、ありがとうございました。 「第4回 親子で学ぶ小牧中特別講座」チラシ完成! ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。 右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 <a href="<b>10/31(木)第4回親子で学ぶ小牧中特別講座が開催されます。</b> ご案内のチラシを作成しましたので、近日中にお子さんを通じて配布させていただきます。 右欄の「配布文書」でもご覧いただけます。 (第4回特別講座チラシ) 今回の講師は、「愛マップ・プロジェクト」ですっかりおなじみの関西大学の城下英行先生です。 「愛マップ」の活動に寄せる想いや、防災の専門家として、日頃取り組まれている研究のことなどをお話ししていただきます。 当日は、「文化祭・夜の学校開放」も合わせて実施します。(18:00〜) 「PTA作品展」会場にて、「愛マップ・プロジェクトの活動報告」のパネル展示を行いますので、ぜひご覧ください。 ● 日時、会場 10/31(木)19:00〜20:00 多目的室 どなたでもご参加いただけます。 事前の申込も不要ですので、お気軽にご参加ください。 【生指】10/10 登校指導   つい先日、登校マナーについての苦情があった、ということを「PTAの部屋」でも話題にしたところです。 先生やPTAが見ている限りでは、ほとんどの生徒が交通ルールを守った登校ができている様子でした。 大人が見ていない時でも、きちんと「交通ルールのABCDの原則」を守って登下校して下さいね! 写真は、上から順に、以下の場所です。 <上段> サントー石油前 <中段> 小牧高校北大輪会館前 <下段> 小牧警察署交差点 朝早くから参加して下さった、当番の生徒指導委員の皆さん、先生方、そして取材して下さった広報委員の皆さん、ありがとうございました! ABCDの原則 〜交通ルール編・また〜 (【小牧中HP】通学状況の話 10/9) 牧中生の登下校のマナーについて、地域の方から苦情のお電話を受けていることは、たびたび学校HPの記事になってきましたし、「PTAの部屋」でも話題にしてきました。 学校では、先生方が事あるごとに指導をして下さっていますが、やはり一朝一夕に解決できる問題ではないようです。 言うまでもなく、通学路となる道路は「公道」で、みんなで使うものです。 公共の場でどのような行動をとるべきなのか、ということは、中学生の皆さんなら言われなくてもわかっているはずです。 今一度、小牧中で取り組んでいる「ABCDの原則」を思い出して、「公共の場での当たり前」が「ちゃんとできる」姿をみせてほしいと願っています。 一人一人が「ABCDの原則」を心がければ、きっとその姿勢が周りにも広がり、「ちゃんとできる牧中生」でいっぱいになるはずです。 また、保護者として、子どもたちに伝えたいのは、 「ABCDの原則で交通ルールを守る=自分の命を守る」 ということです。 通学路を道いっぱいに広がって歩くことは、他の人の迷惑になるばかりでなく、交通事故の原因にもなりかねない危険な行為であることを、しっかり自覚してもらいたいのです。 この機会に、ご家庭でも、ぜひお子さんと一緒に考えていただけるといいですね。 親の想いを、お子さんに伝えて下さい。 昨年、「PTAの部屋」で、登下校のマナーについての記事を書きました。合わせてご覧下さい。 (【PTAの部屋】ABCDの原則〜交通ルール編・再び〜 2012/6/15) 「四つの空 いのちにありがとう」 「一生懸命生きることが大切」「親より先に死んではいけない」というメッセージは、大人だけでなく、子どもの心にも強く印象に残りました。 (【PTAの部屋】新しいこと始まりました!「第3回親子で学ぶ小牧中特別講座」 8/21) そんな鈴木さんが代表を務めておられる「いのちをバトンタッチする会」が映画を製作した、というニュースが、昨日(10/3)の中日新聞に掲載されていました。 「四つの空 いのちにありがとう」という映画です。 これは、四つの懸命に生きるいのちと、それを温かく支える家族の物語だそうです。 鈴木さんは「多くの人に見てもらい、自分がどう生きるかを考えるきっかけにしていただければ」と話されています。 ※HP(以下のリンクをクリックして下さい↓)では、予告編(4分30秒ほど)が見られます。 新聞に掲載されていた、主な上映会の日程を引用します。 関心のある方は、「いのちをバトンタッチする会」HPをご覧ください。 *****以下、引用***** ■主な上映会の日程 【10月】 ▽5日後3、長野市ふれあい福祉センター ▽6日前10、後1・30、長野県小布施町、新生病院 ▽11日後6・30、東京都港区赤坂、匠ソホラ ▽13日前9、埼玉県嵐山町、国立女性教育会館 ▽25日後6、愛知県みよし市、みよしサンアート ▽26日前9・45、名古屋市中村区、ウインクあいち 【11月】 ▽12日後7、東京都板橋区立文化会館 ▽17日後2、名古屋市中村区、ウインクあいち ▽24日後2、東京都千代田区、日比谷図書館 【12月】 ▽18日後6・30、愛知県瀬戸市、瀬戸蔵つばきホール *****引用ここまで***** ※写真は、10/3中日新聞朝刊から引用しています。 9/30 ミニミニ講演会(2) 〜校長先生編〜 【校長先生編】 校長先生は、今、話題になっている「全国学力・学習状況調査」についてお話しして下さいました。 先日、お隣りの某県知事が「小学校の国語Aの問題で、平均点以上だった上位100校の校長名を公表する」ということが話題となりました。 当初は、結果が全国最下位だったことに激怒した知事が「成績が悪かった学校の校長名を公表する」と言ったことで、大きな騒動となったのですが、最終的には「褒めるために、上位100校を公表」ということで落ち着いたようです。 そんな「全国学力・学習状況調査」ですが、実は、知事が激怒して大問題にするほど、結果には差がないんですよ、ということを、校長先生は教えて下さいました。 「平均正答率」という数値があります。 全問題数のうち、何問正解したか、という割合です。 例えば、全問題数10問のうち、正解したのが6問なら→60% これが愛知県の「平均正答率」だったとして、仮に「全国平均」が66%なら、愛知県は「-6%」ということになりますね。 都道府県別に見てみると、この「平均正答率」が「全国平均」よりも「-5%以下」だった都道府県は、減少しているのです。 小学校では、国語も算数も「-5%以下」の学校がなくなり、中学校でも「国語B」で「-5%以下」の学校がなくなったとのことです。 要するに、ほとんどの都道府県が「全国平均」と同じか、それ以上の「平均正答率」だった、ということですね。 このことからわかるのは、実はそれほど学力に差がついているわけではない、ということです。 テストですから、順位が出ます。順位というのは、必ず1位がいれば最下位もいるわけです。 順位だけ見れば「最下位」かもしれませんが、内容はそれほどの差ではなく「問題が1問解けていたら、順位もぐーんとアップする」という状態なのです。 玉置校長先生が子どものころにも、このような学力テストがあったそうですが、いつのまにか「テストのための勉強」が常態化してしまい、本来の学力を調べるためのテストではなくなってしまい、廃止になったそうです。 今行われている「全国学力・学習状況調査」も、同じようなことにならないといいですね。 マスコミは「順位」について騒ぎたてますが、そこにだけ気を取られずに、国が子どもに求めている学力(B問題のような応用力を重要視していると言われています)について、成果があがっているのかどうか、という見方ができる保護者になりたいものですね。 校長先生には、数学Bの問題を見ながら、解説していただきました。 教科書に出てくるようなわかりやすい問題ではありません。 長い長い文章題で、イラストもあれば、関係ありそうな数字もたくさん出てきます。 このような問題を解くには、「資料や問題文から、何を問われているのか読み解く力」が必要ですね。 そして、実際に問題を解くときには、すばやく「必要なものを見極める力」「必要な情報だけを使う力」も必要になります。 これらの文章題を解くためには「言語力」が大切だ、と校長先生はおっしゃいました。 この「言語力」を高めるためには、「単語だけ」の会話ではダメなのです。 ですから、授業中、先生方は子どもたちができるだけ「文章」で答えられるように気を付けているそうです。 そのような取り組みのおかげで、小牧中の応用力のレベルは悪くはないそうですよ。ホッとしましたね。 また「授業中に友達と話し合っていますか」という設問の回答が、小牧中の数値は全国的に見ても高いので安心して下さい、とのお話しもありました。 これは、小牧市内の小中学校で取り組んでいる「学び合う学び」の効果が出ているということなのでしょうね。 このように、校長先生が調査結果の見方を教えて下さったおかげで、子どもたちの学力はそれほど悪くないようだ、ということがわかりました。 「順位」にばかり気を取られていると、本質的なことに気がつかないまま過ぎてしまいますね。 中学生は、定期テストごとに「順位」が出て、そのたびに一喜一憂しますが、順位ばかりでなく、テストの内容(できたところ、できなかったところ)をきちんと見直して、次につなげられるようにしていきたいですね。 今回の校長先生のお話しも、楽しく「親が学べる」内容でした。 お忙しい中、PTAのためにお時間を作っていただいた五島先生と校長先生、ありがとうございました。 そして、今回も多くの保護者の皆さんにご参加いただき、役員一同、とてもうれしく思っています。 皆さん、ありがとうございました。 9/30 ミニミニ講演会(1) 〜五島先生編〜 今回ご登壇いただいたのは、五島縁先生と玉置崇校長先生のお二人です。 五島先生は、1年8組担任で、演劇部の顧問をされています。 新1年生の保護者には「はじめまして」の方も多いと思いますが、上級生の保護者にはおなじみの先生です。 そんな五島先生の「私の歩んできた道」をたっぷりとお話しいただきました。 【五島先生編】 実は、五島先生は新任で小牧中へ来られて、今年6年目です。 見るからに超ベテランなので、「えっ?新任?」と思われる保護者も多いと思います。同期は、同じく1年生担任の伊藤陽平先生です。 五島先生は、なんと40代になってから教員になられたのです。 まずは、ご自身の子どもの頃のお話から。 五島先生のご実家が学習塾を経営されていた関係で、自分が子どものころから中学生と関わることが多かったそうです。 その当時から「中学生は何でもできて、スゴイ」というあこがれの存在だったそうです。 しかし、教員の道には進まず、一般企業の理系の研究部門に就職して7年間勤務されましたが、体調を崩されて退職し、ご実家の学習塾を手伝うことに。 ご実家の学習塾では、ご両親を手伝いながら、最後は引き継いで、結局15年ほど続けたそうです。 学習塾の仕事を続けながら、日中は事務のお仕事をされたり、通信教育の添削のアルバイトをされたり、子育てをしながらいろいろなお仕事を経験されたそうです。 その中でも、金城学院中学の非常勤講師を2年された経験から「担任を持ちたい」という気持ちが起き、教員採用試験の受験資格が変わったことを追い風に、挑戦されたそうです。 学習塾やクラス担任では、子どもとの距離がとても近いのですが、非常勤講師ではやはり距離が遠く、関わり方も薄くなってしまうと感じられたとのこと。 これまでの経験から、「もっと子どもと積極的に関わりたい」と思われたのですね。 教員採用試験はとても難しく、何年も挑戦し続けている先生が多い中、一度で合格するというのは、五島先生の実力と努力はもちろんですが、さまざまな経験が活かされていたのではないかと感じました。 実際に教員になって感じたことは「とにかく先生は忙しい」ということだったそうです。 こんなに忙しくて大変な仕事だとわかっていたら受験しなかった、とおっしゃっていました。 とくに新任のときは、自分が何をしたらよいのかわからず、聞きたくても忙しそうにしている先生方には声をかけづらい。私はここにいる意味があるのか、と苦しい思いをされたそうです。 ですから、今、若手の先生方には、気持ちがわかる分、積極的に声をかけてあげているそうです。 もともと、五島先生には「子どものそばにいたい。関わっていきたい」という思いがあり、もちろんご自分のお子さんに対しては「我が子の幸せを願う」お母さんでもあります。 「自分の子どもの幸せを願うならば、社会全体が幸せにならないといけない」とおっしゃった言葉にハッとしました。 子どもは、親だけでなく、学校の先生や地域の大人たちなど、多くの社会の人々の中で成長していくものですから、社会全体が幸せにならないと幸せな子どもが育たない、ということですね。 子どもたちは、親など身近な大人の言うことはなかなか聞けないけど、他人であれば素直に受け入れたりできる部分があるので、そのお手伝いができれば、という気持ちもあり、教員になられた、とお話しして下さいました。 そんな五島先生ですが、教え子との悲しい別れを経験して、より一層、一生懸命生きようと努力されているそうです。 人の命は、必ず終わりがあります。 命ある限り、一生懸命生きて、いつか天国で教え子に再会した時に、恥ずかしくない生き方をしようと誓った、と話される姿は、とても頼もしいものでした。 「彼の分までがんばるぞ」という強い気持ちを持たれているんだな、と感じました。 五島先生は言います。 「学校の先生方は、とにかく忙しくて、土日も部活動をやっていたり、なかなか休みも取れない。それでも、『子どもたちのために』という思いで、毎日がんばっているんです」 そんな先生方に、子どもたちは育ててもらっているのですね。 若手の経験の浅い先生にも、五島先生のように気さくに声を掛けてくれてしっかりフォローしてくれる先輩先生がついていてくれるんだ、という、学校のしっかりしたフォロー体制がわかり、私たち保護者も安心して子どもを学校に預けることができますね。 今回も、五島先生の人柄がとてもよくわかり、先生が身近に感じられる、とてもよいお話しを伺うことができました。 五島先生、どうもありがとうございました。 9/30 第2回PTAサロン 今回も「多目的ホール」での開催となり、ご参加いただいた保護者の皆さんには、広い会場でゆったりとくつろいでいただけました。 そして、前回と同様に、開催時間を延長して授業参観終了時までとしたので、参観の前後に気軽に寄っていただくこともできました。 「ミニミニ講演会」の開催時間に合わせてご来場いただく保護者も多く、座席が足りなくなるほどでした。 この「ミニミニ講演会」については、後日まとめの記事をアップする予定ですので、しばしお待ちを! 今回も、PTA役員の皆さま、地域コーディネーターの皆さま、学校からは岩田先生や山口先生に、準備から後片付けまで、大変お世話になりました。 ありがとうございました。 多くの保護者の皆さんにご利用いただけたことが、次回への励みになりました。 本当にありがとうございました。 9/30 第2回制服等リサイクル販売 「多目的ホール」へ会場を移して2回目の開催だったので、保健委員の会場準備もスムーズに完了することができました。 PTAサロンとリサイクル販売の、両会場を行き来する保護者の姿が多く見られ、たくさんの皆さんに参加していただくことができました。 リサイクル品が不足しています! 多くの方がご利用いただけるように、ご家庭に眠っている「牧中グッズ」がありましたら、ぜひご提供ください。 保健委員の皆さん、準備から後片付けまで、本当にありがとうございました。 |
小牧市立小牧中学校
〒485-0046 小牧市堀の内四丁目30番地 TEL:0568−77−6321 FAX:0568−75−8295 |
|||||